蔦屋重三郎は若い時は吉原の引手茶屋の仕事の傍ら、行商の「貸本屋」も行っていたようです。
「貸本屋」は落語の中にも登場しますね。
「品川心中」の金蔵、「紙入れ」の新吉(演者によっては「小間物屋」だったり「呉服屋」だったりするのですが。)また三遊亭圓朝・作「真景累ヶ淵」の新吉も煙草屋の前には「貸本屋」に奉公していたという。
江戸時代「貸本屋」の需要はどのくらいのものだったのでしょう?
江戸庶民に本が読まれるようになったのは江戸時代中期。
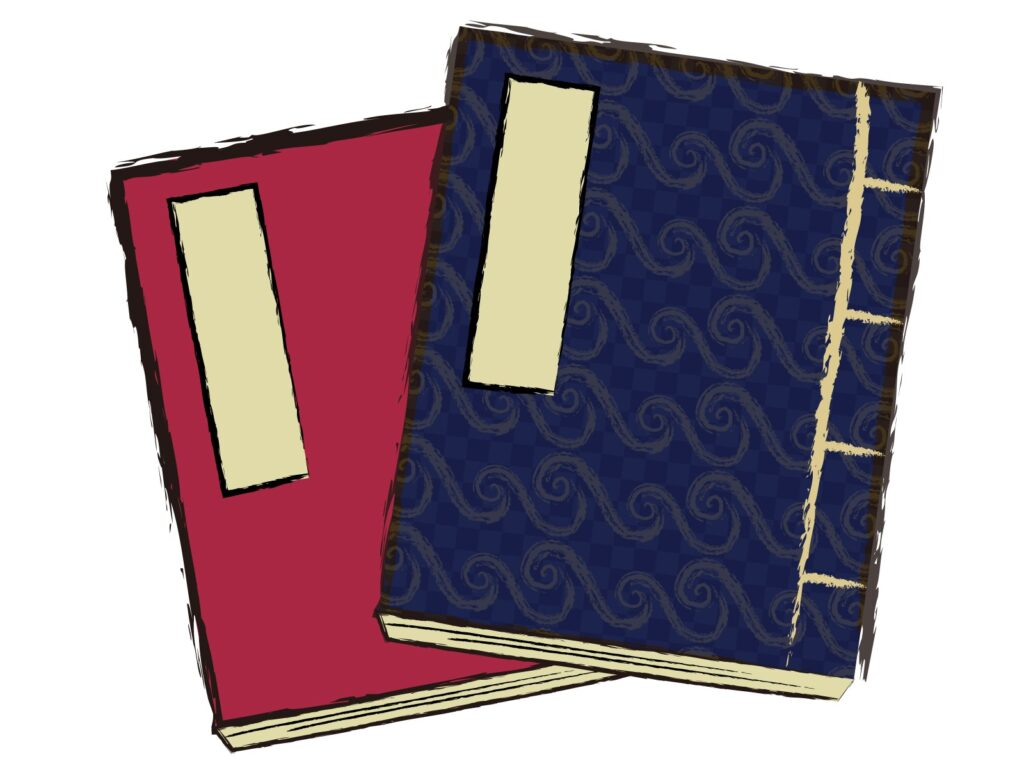
それ以前の出版物は公家、武家、僧侶など特定の知識階級の人たちだけのものでした。そのため、出版されていたものも学術書や仏書などがメインでした。
しかし、元禄時代に入り、町人文化がメインになり、絵本をはじめ、怪奇物や滑稽本など、読み物が増え、庶民が楽しめる本がたくさん出版されるようになりました。そして、一気に庶民の間で読書が流行りだしたそうです。
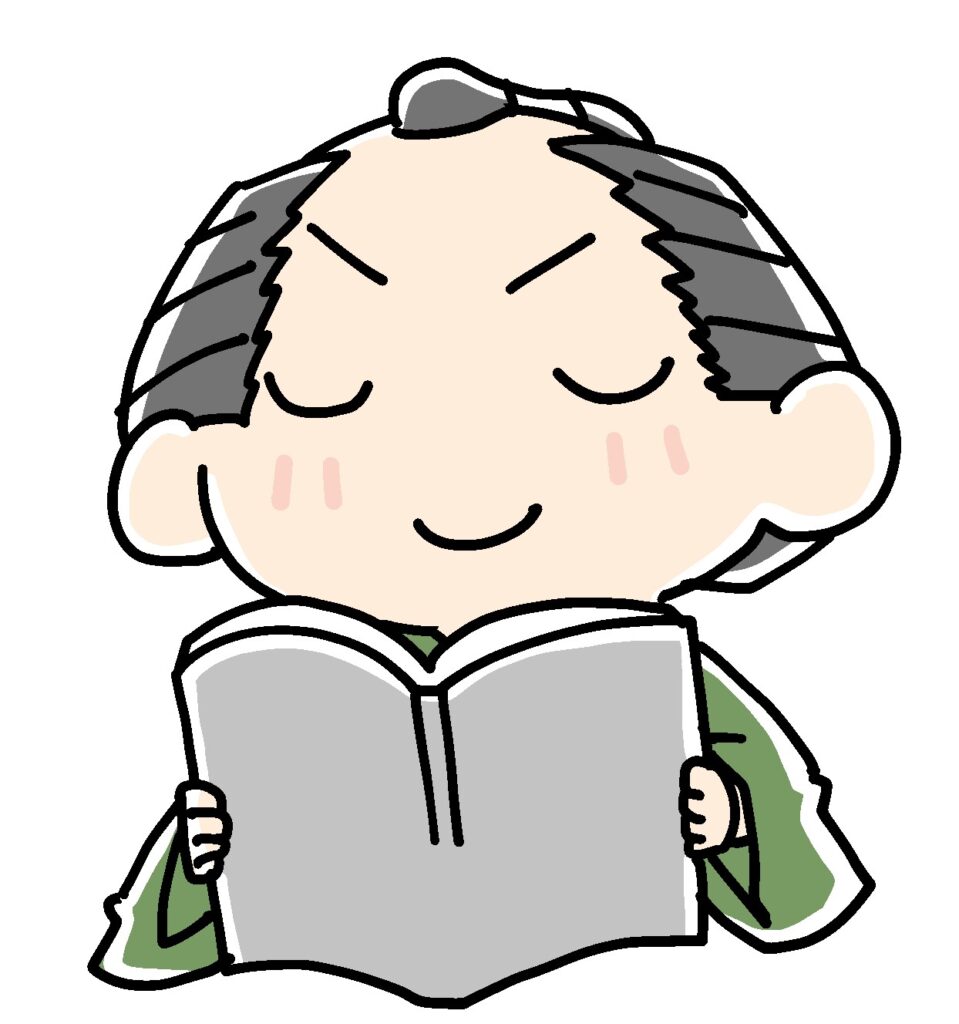
庶民にとって本が身近なものになったとはいえ、やっぱり江戸時代の書籍はまだまだ高価でした。本の値段は蕎麦の値段の何十倍や何百倍もしたというから驚きです。
そこで発達したのが貸本です。借りている期間に応じてを払うとい借り賃を払ううシステムです。
子供向けの赤本(おとぎ話、民話を題材にした絵本)、青本(浄瑠璃・歌舞伎・軍記物などを翻案・簡略化したもの)、浄瑠璃本・洒落本(遊里での遊びと滑稽を描写した読み物)・読本(歴史や伝記などを題材にした物語風の読み物。)を一冊六文~二十四文、高いもので七十二文で貸し出していたそうです。
浄瑠璃本といいますとドラマ中で座持花魁うつせみ(小野花梨)が「『ひらかな盛衰記』はあるかい?」と尋ねる件がありましたが、これも時代を象徴したセリフで興味深かったですね。
「ひらかな盛衰記」は1739年(元文4年)に文耕堂・三好松洛・初代竹田出雲・竹田小出雲(後の二代目竹田出雲)の合作で大阪竹本座で初演された作品で「源平盛衰記」をその当時の庶民にもわかりやすく伝える意図で書かれたそうです。歌舞伎でも上演され特に四段目「神崎揚屋の段(無間の鐘)」の遊女梅ケ枝は平賀源内(安田顕)がこよなく愛した当時人気の女形役者の二代目・瀬川菊之丞が当たり役としたそうです。 人気役者が売り物にしていた芝居の原本としてどんな話か読んでみたいと思う女性は多かったでしょうね。
ドラマの中の綾瀬はるかちゃんのナレーションでは当時は蕎麦一杯が十六文だったの「貸本屋」はちょいとした小遣い稼ぎだったと語ってましたが、落語の出てくる金蔵さんや新吉さんのように「貸本屋」を本業としていた人はどうだったのでしょうね。
仮に一番高い本(72文)の貸し出しが一日一回あったとして30日で2,160文すなわち2分ぐらいの稼ぎってことになりますね。実際はもっとあったかも知れませんが。杉浦日向子先生の「一日江戸人」のよると月400文の店賃の長屋に住んでの生活をしてても2分でも黒字の生活ができたようですから、まあなんとかやっていけるレベルの生活はできたことでしょう。でも金蔵さんのように品川の遊女に入れあげているような男はそれなりに赤字になっていたかも知れないし、新吉にようにお得意さんに可愛がられ、そのお内儀さんに必要以上に可愛がられてしまう男は更に良い生活ができたかも知れませんね。
「読む」楽しみを商う「貸本屋」さんはその時代の浮世絵などでみると下記のリンクの先にあるような粋な感じになっていますけど、中にはそうでないのもいたかも知れません。
https://radonna.biz/blog/wp-content/uploads/2020/12/honya-22-1024×731.jpg
「品川心中」の金蔵さんは、二代目・三遊亭金翁師演の中の品川の白木屋お染の言葉を借りて言うなら「ケチ」「醜男」「大飯喰らい」というおよそご婦人にモテない要素の揃った殿方のようで。 お染さんも「醜男」だから心中相手としては嫌だけどこういう「大飯ぐらい」が一人死ねばお米の相場も安くなるだろうから、仕様がないから心中相手はこの人に決めようと言っているぐらいですからね。
逆に「紙入れ」の新吉は自分を可愛がってくれている得意先のお内儀さんと出来てしまうくらいですから上記リンクの絵のような感じかも知れませんね。
真景累ヶ淵」の新吉も貸本屋に奉公している時に出先の深川の櫓下の花街にいたお賤と顔見知りになり、やがては下総羽生村で名主惣右衛門の妾となったお賤と再会し密通、その挙句に二人で惣右衛門を殺害するなどの悪事を重ねていくのですが、やはり「紙入れ」同様粋な感じの「貸本屋」さんっだったかも知れません。
ちなみに某AIに江戸時代の「貸本屋」のイラストの作成を頼んだら下記の通りの画像を作ってくれました。
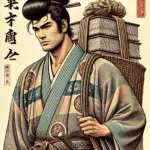
こんな感じの「貸本屋」さんがいなかったなんて断言はできませんがね。
」
蕎麦一杯が十六文だった江戸時代においてちょっとした小遣い稼ぎだったと綾瀬はるかちゃんのナレーションにありましたが、
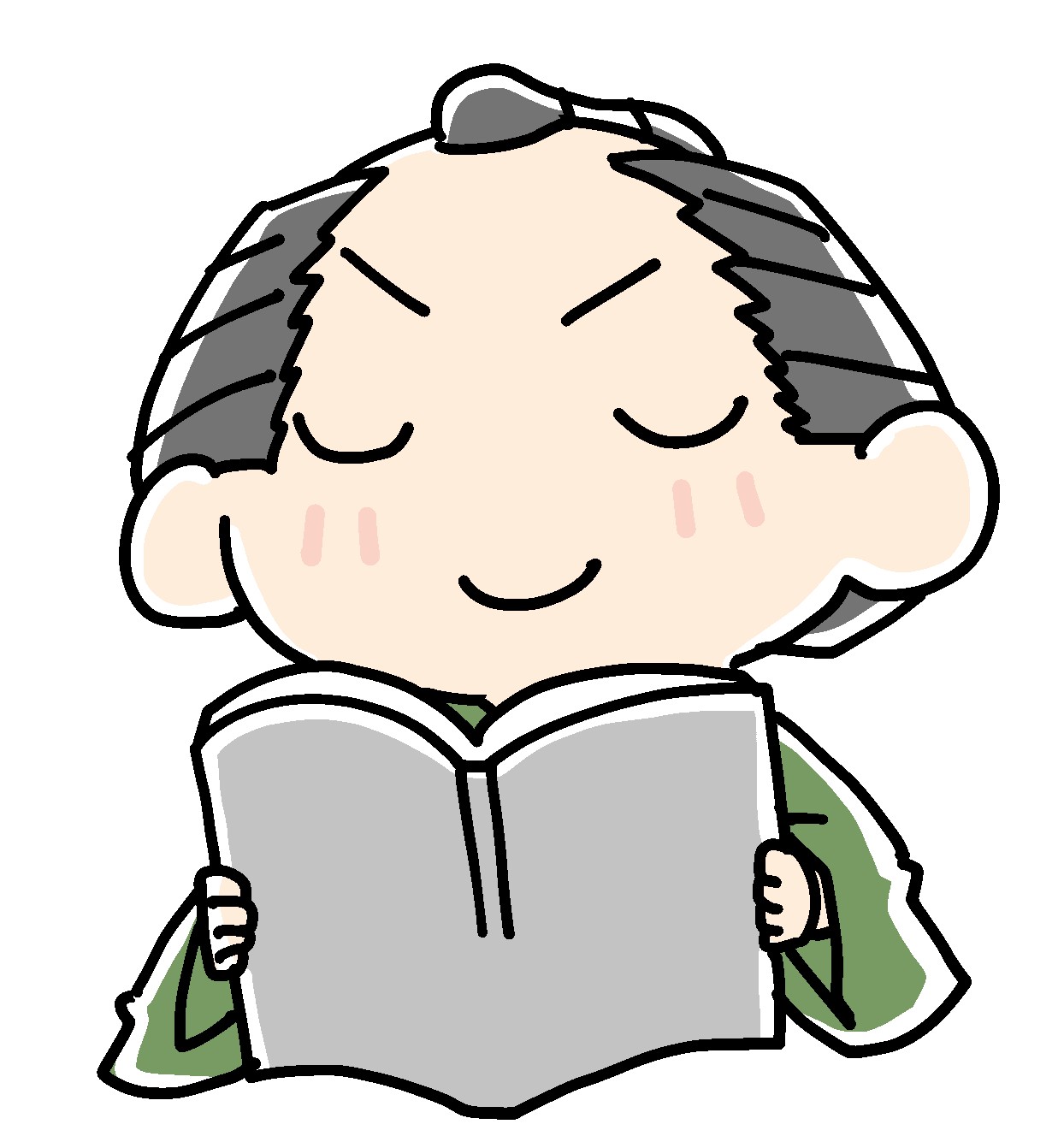


コメント
♪♪♪ 梅が枝の~手水鉢 叩いてお金が出~るならば ♪♪♪
四段目「神崎揚屋の段(無間の鐘)」というと落語では『搗屋無間』(別題『無間の臼』)に登場します。
現代ではほとんど演り手のない絶滅危惧落語ですが、あたくしは『紺屋高尾』や『幾代餅』よりも好きです。
二代禽語楼小さんの『無間の臼』では、「昔梅が枝という女郎は無間の鐘を叩いて三百両の金を得たということは浄瑠璃や講釈で聞いたが……」と浄瑠璃や講釈で聞いたとあります。
四代橘家圓喬は『搗屋無間』で、「考えてみるといつか芝居で見た花魁が無間の鐘を搗いたというのはこれだ。あれは修羅の地獄へ落ちても構わねえといって、三百両の金で鎧を受け出したいばかりに無間の鐘を搗いたというが、ウーン搗くのは俺の商売だ。三百両なくっても一割の三十両もあれば二日遊べる。たとえ梅が枝だって俺だって、思う心に変わりはねえ」とこちらは芝居で見たと言わせてます。
また圓喬は『淀五郎』のマクラで二代ではないのですが、三代瀬川菊之丞が芸に目覚める逸話を紹介してます。
拙ブログで『搗屋無間』をアップしてますので、お暇の時にでも。m(__)m
https://ameblo.jp/tachibanaya-dasoku/entry-12766339335.html
立花家蛇足さん
いつもコメント頂きありがとうございます。
> 絶滅危惧落語
「搗屋無間」がほとんど演じられないのは、一つはネタとなっている「ひらかな盛衰記〜神崎揚屋の段(無間の鐘)」という芝居自体が「仮名手本忠臣蔵」のような人気芝居に比べると現代は上演回数が少なく、その結果「無間の鐘」に関してもあまり知られてないということもあるかも知れませんね。
上記の芝居に関しては私は一度歌舞伎座で四代目・中村雀右衛門丈の舞台を
観たことがあります。
その時のパンフレットに上演の記録が記されていたのですが、特に昭和以降は六代目・中村歌右衛門丈、四代目・坂田藤十郎丈たちによってたまに上演されているぐらいなんですね。
「搗屋無間」に関しては八代目・春風亭柳枝師演の他、六代目・三遊亭圓窓師演をNHKテレビ「日本の話芸(NHK東京落語会)」で視たのですが、出てきた金は実は親方が天井裏に隠していたヘソクリだったという設定になってました。
ヘソクリが皆にバレてグゥの音も出ない親方の目の前でお内儀さんが三百両のうち二百七十両を主人公に渡して「一割の搗き減り」のサゲに持って行ってました。
蛇足さんのブログもまた拝見させて頂きます。
また私のブログにもお時間ある時にお寄り下さい。
Hello! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website?
I’m getting fed up of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m
looking at alternatives for another platform.
I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.
I enjoy how your words reflects your individual personality. It feels like we’re engaging in a meaningful conversation.
I love how you incorporate your personality into your posts. It seems like we’re having a friendly chat over coffee.
Thank you so much for your kind words. I will continue to write my best
I love how you imbue your writing with personality. It feels like we’re having a delightful conversation.
Thank you so much for your kind words. I will continue to write my best
You have an remarkable ability to transform ordinary topics into captivating content. Keep up the outstanding work!
Your blog consistently captures my attention, compelling me to devour every word from start to finish.
Your dedication and enthusiasm shine through in every section you write. It’s infectious!
Thank you so much for your kind words. I will continue to write my best
You’ve provided invaluable insights that will certainly help me in my work.
Thank you so much for your kind words. I will continue to write my best
Your blog is refreshing. The quality of your writing makes visiting a delight.
Your writing creates vivid imagery in my mind. I can visualize every detail you describe.
Your content offers something for everyone; it’s helpful for both experienced and novice readers.
Thank you for making me rethink my perspective to this topic; your insights are priceless.
Your words can paint vibrant pictures in my mind. I can visualize everything you portray.
Your post has got me thinking. We didn’t considered things in that way. The author have broadened our perspective. Thanks.
You have an impressive skill to communicate complex concepts in a straightforward manner.
Your writing resonates with me; it feels like you comprehend my challenges.
Your writing style is absorbing; it feels like having a chat.
I truly enjoyed reading this article and discovered some useful information. Thanks for sharing your insights with your readers.
Your skill to captivate readers with everyday subjects reflects your impressive communication skills. Well done!
Your blog has quickly become my favorite source for motivation. I thank you for sharing your thoughts.
Thanks a ton for sharing this valuable post. Your opinions are very thought-provoking and the content is clearly crafted. Keep it up!
Your style is captivating, I couldn’t stop reading.
Your writing style is captivating; it feels like having a conversation with a pal.
Your devotion and enthusiasm truly stand out in every paragraph you write. It’s remarkable.
I appreciate the time you put into providing all the required facts.
Your website feels like a fountain of information and inspiration. Thank you for presenting it with us.
You’ve managed to combine expertise with a casual approach, making it a delight to read.
Your tips are applicable and pragmatic; I can see myself implementing them easily.
This site offers an abundance of valuable information on a variety of subjects. Thanks for all that you do.