1月5日放映第一話「ありがた山の寒がらす」
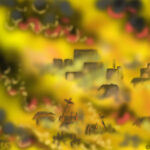
オ―プニングがいきなり「吉原の火事」なんですね。
明和9年2月29日に発生した「明和の大火」だそうですね。「明暦の大火」「文化の大火」と並んで「江戸の三大大火」と言われているそうです。
出火したのは目黒の大円寺。
武州熊谷無宿の真秀という僧が盗み目的で放火したのが南西の風の影響で麻布、京橋、日本橋へと被害が及び江戸城下の武家屋敷を焼き尽くし、神田、千住まで燃え広がってたという。途中二回程、鎮火を見せながらも再出火し、駒込、根岸まで被害が及んだそうです。
現在の東京23区を斜めに縫うような被害だったわけですね。
吉原遊廓へも被害があったのですが、ドラマでは主人公の蔦屋重三郎(横浜流星)が懸命に半鐘を叩き、花魁花の井(小芝風花)がお稲荷様を火事から守ろうとその場を離れようとしない二人の禿を早く逃げるように促している場面がありました。

視ていて不思議に思われた方もいると思いますが、火事なのに「火消し」が活動している場面がないのですね。
林家彦六師が三遊亭圓朝・作「粟田口霑笛竹〜丈助の最期」の語り出しで「昔は吉原に火事がありますと火消しは手を出しません。燃えっぱなし・・・・・。」 と 言っていたのを思い出しました。
「徳川制度」の資料によると江戸時代の吉原で火事が発生した際には、火消しが建物を破壊して、消火することはなく、燃えるに任せて放置する決まりだったそうです。
これは、吉原が全焼すると仮宅で営業することが許可されていたためと考えられます。
仮宅は遊郭にない素人の家のような雰囲気や情緒があり、格式張らないことで人気を集めて賑わいました。また、仮宅営業中は万事が質素で、揚代金や雑用金も手軽になるため、一時は 格別の賑いになるのが一般的でした。 すでに衰えた遊女屋も類焼後かえって繁盛して、身上を取直すこともあった」とあり、仮宅で営業したほうが儲かったようなのですね。
廓内に失火があると、廓内の消防夫が消防に従事し、御府内四十八組の火消も直ちに繰出されましたが、大門内に入らず、土堤に陣取って鎮火を待ったとされています。

「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺」の第一回放送では、落語の「品川心中」「紙入れ」で出てくる「貸本屋」や日本橋浮世小路の懐石料理屋「百川」が出てきて、落語好きの私が視ていて興味惹かれる部分がかなりありました。
またその辺も取り上げてみたいです。



コメント
あたくし実は、落語よりも、吉原研究が本職でした。(^^)
いわゆる遊郭です。
浅草田圃の新吉原で最初の大火(全焼)は、1676年(延宝4年)12月でした。
そして、次は88年後の1764年(明和元年)4月で、以降はほぼ5年ごとに吉原は全焼しております。
この1764年というのは、吉原で圧倒的な力を持っていた揚屋が太夫の名称とともに消失した年でもあります。
それまでは懸命に火を消していたため、88年間ボヤ程度で済んでいましたが、揚屋が無くなって以降は、火付けもありますがある程度の火事で消火しては、燃えた遊郭と無事だった遊郭の間に不公平が生まれるため、燃やすに任せたのが実情です。
しかし、仮宅のある遊郭はいいですが、それ以外の茶屋やその他の店(仕出し料理の台屋、菓子屋、湯屋などなど)はたまったもんではありません。
1796年(寛政8年)に吉原内で「新吉原町規定証文」を出し、熱心に消火活動をするよう遊郭内で申し合いましたが、有名無実だったようです。
実は1875年(明治8年)12月12日 午後0時5分に出火し吉原がほぼ全焼しました。出火元は『文七元結』でおなじみの佐野槌の台所でした。
1880年(明治13年)佐野槌は店を畳みました。
貸本屋、圓喬の速記で『貸本屋の夢』というものもあります。(^^)
立花家蛇足さん。
ありがとうございました。
林家彦六師演の「粟田口霑笛竹〜丈助の最期」をLPで聴いたのは中学生の時で「吉原に火事があると火消しは手を出さなかった。」事を聴いた時は「どうしてなんだろう?」と思いました。
「管轄」の問題とかもあったのかななんて思ったりもしましたが、「不公平」を避けるという問題もあったのですね。
「文七元結」で情の厚い女将さんが仕切っている「佐野槌」がまた「火災」の問題を起こして閉店になっていたとはねえ。
「赤線禁止法」が出来て数年後にこの世に生を受けた私は立花家蛇足さんから「吉原遊廓」について教わりたいことが色々あります。
またちょくちょく起こし頂きコメント頂けれは幸いでございます。