先月NHKテレビ「ブラタモリ」で「大山詣り」やっていたのを録画したまま見ずにいつたのできょうみてみたのですが。
サブタイトルは「粋でいなせな大山詣り」としてありました。

「大山詣り」は江戸時代に江戸っ子の間で大流行したそうです。大山(神奈川県伊勢原市)への参拝を兼ねた行楽で、地理的にも江戸から比較的近く、その当時でも1泊2日で行けたそうで。また、参拝後に江ノ島、鎌倉を観光するなど手軽にレジャーも楽しめることから、信仰と観光の両面で人気を集めたそうですね。
大山詣りは、江戸時代の人々の信仰心とレジャーへの欲求を満たし、江戸文化の一端を担う存在となりました。
そしてその文化的価値が認められ、日本遺産に認定されています。
そんな「大山詣り」を背景にした次の噺を今回は取り上げます。
長屋の連中が今年も大山詣りをすることになった。しかし、毎年のように途中で喧嘩騒ぎがおこり、特に先達の吉兵衛さんに迷惑をかけている。そこで旅の間に腹を立てたら二分ずつ罰金、暴れたら坊主になるという決まりをつくる。
好天に恵まれ行きは良い良いで何事もなく、無事に大山に上って下り、東海道の藤沢宿に出た。今年は喧嘩騒ぎもなく、江戸に帰れると思った矢先の神奈川のなじみの宿で、気が緩んで酔った熊さんなる男がは暴れて大立ち回りで、殴られ蹴られた被害者が続出だ。
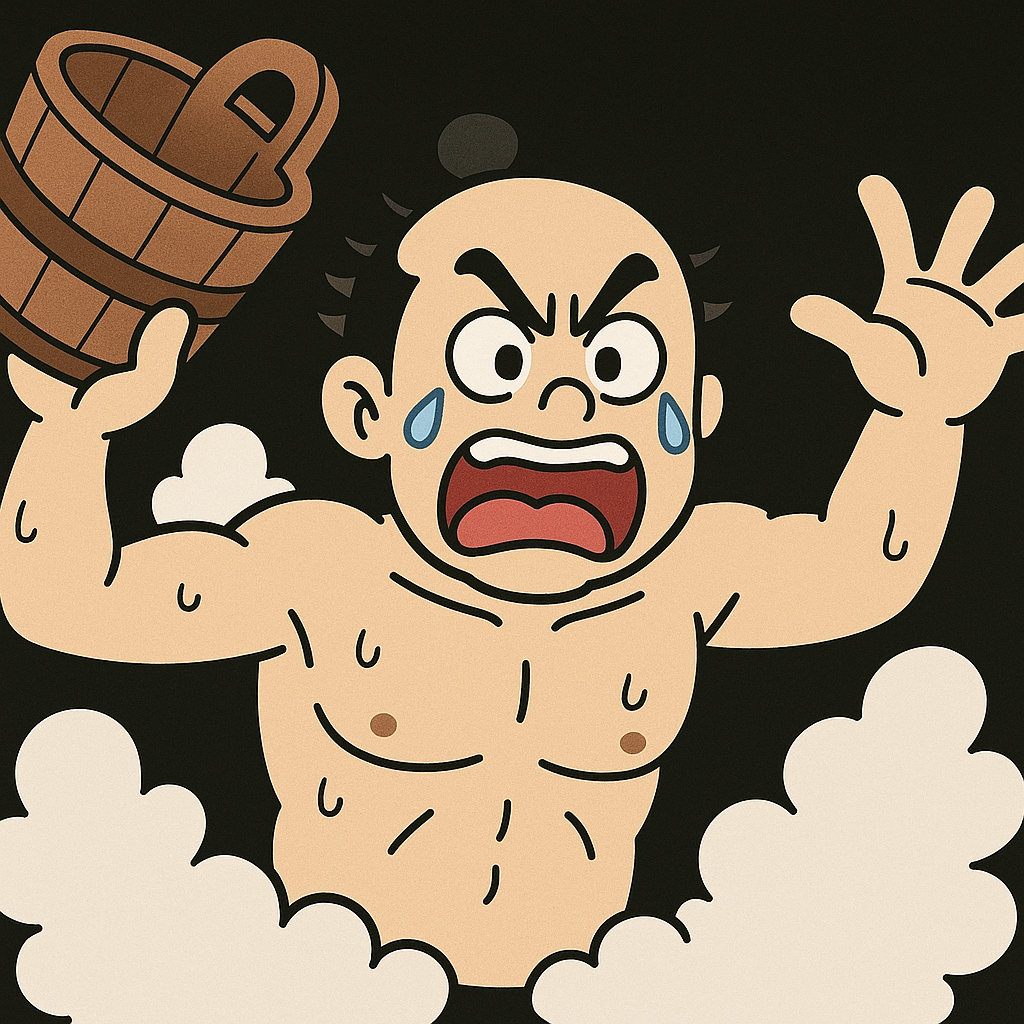
吉兵衛さんは江戸も近いことだし、穏便に収めようとするが、殴られた連中はとても収まりがつかない。約束通り腹を立てた自分たちは二分づつ出すかわりに酔い疲れ、暴れ疲れで二階で大いびきをかいて寝込んでしまった熊さんを寄ってたかってクリクリ坊主にしてしまった。

翌朝、連中はまだ寝ている熊さんを宿に残して江戸に向かった。知らぬが仏の熊さん、起しにきた女中たちが頭を見て、坊さん坊さんと笑っている。頭をさわって愕然、「やりぁがったな」と、すぐに通しの三枚の駕籠を仕立て一目散に江戸へ向かった。途中、のんびり道中の長屋の連中を追い抜き、一人で血相を変えて長屋へ駆け込んだ。
長屋のかみさん連中を集めて、わざと悲痛な顔で、「お山の帰りに寄り道して金沢八景を見物して、舟に乗ったが嵐になって舟は転覆、自分一人だけ浜に打ち上げられて助かった。村人の話では他の連中はみな溺れ死んだという。一刻も早く知らせようと通し駕籠をぶっ飛ばして帰って来た」と、作り話をする。
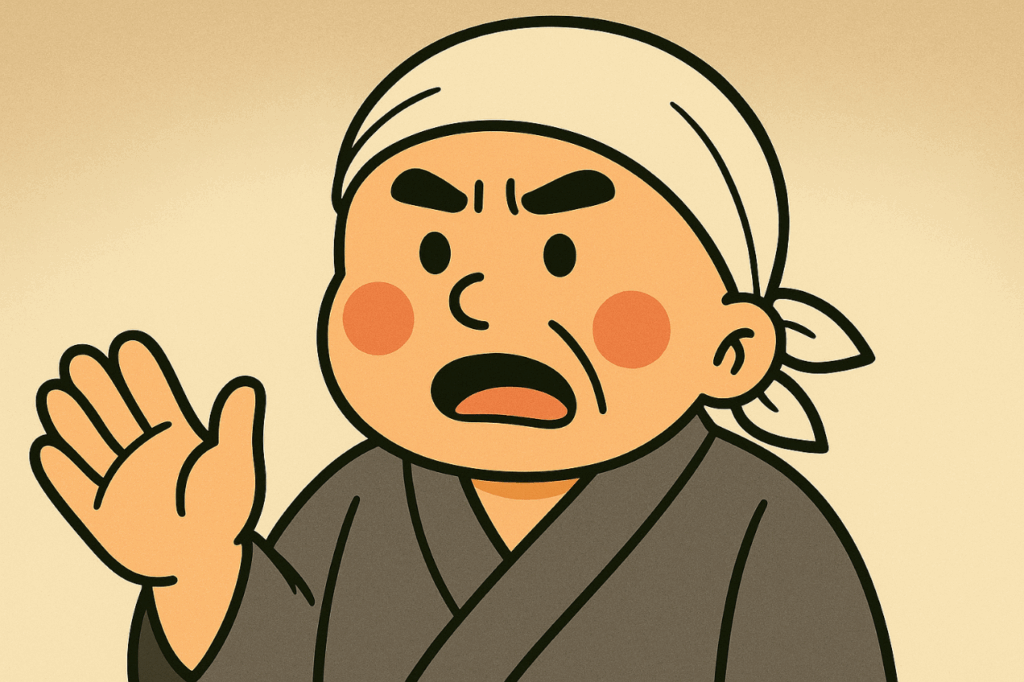
かみさん連中は、すっかり信じ込んでワッと泣きだすが、吉兵衛さんのかみさんだけは信じない。「お前の仇名は「ホラ熊」・「千三つの熊」で嘘つき名人の言うことなんか信じちゃあいけない」と冷静だ。熊さん、そこまで言うならと頭に被っていた手拭を取った。見るとつるつるの坊主頭だ。
熊さん 「これが証拠、死んだ連中へのせめてもの供養のため頭を丸め坊主になったのだ」と、しみじみと言うと、さすがの吉兵衛さんのかみさんも、「あんなに見栄っ張りの熊さんが丸坊主になった。今の話は本当のことだ」と、ワァワァと泣き崩れ、それにつられて長屋のかみさんたちが大声で泣き始めた。

計略は大成功でしめたと熊さん、「それほど亭主が恋しければ、尼になって回向をするのが一番」と、丸め込み、とうとう自分の女房以外のかみさんたちを全部クリクリ坊主にしてしまう。

さて、のんびりと旅の思い出話に花を咲かせながら帰ってきた男連中、長屋に入ると念仏の大合唱、おまけに冬瓜舟が着いたような、比丘尼たちの頭がずらり。よく見ると自分たちの女房が尼さんになって熊さんを取り囲んで念仏を唱えている。熊さんにしてやられたと知った連中は怒り出すが、当の熊さんは「草鞋履いているうちは旅のうちだ。腹を立てたんなら二分ずつ出せ。」にたまりかねた連中、「面倒だ。やっちまえ!」中には溝板を剥がして振り回す奴まで出てくる。

吉兵衛さん 「みんな乱暴はおよし。はっはっは、これはかみさん連中がみんな坊主になっちまったのかい。馬鹿だね、うちの婆さんまで一緒になって坊主になることはねえじゃねえか。これはめでたい。」「カカアを坊主にされて何がめでてえんだよ?」「お山は晴天。家に帰ればみんなお毛が(怪我)なくっておめでたい。」

原話は狂言の演目『六人僧』と推測され、十返舎一九の『滑稽しっこなし』(文化二年・1805年)にも同種の話がある。共立女子短期大学教授 武藤禎夫先生はこれらのほかにの井原西鶴の『西鶴諸国ばなし』第1巻(貞享ニ年・1685年)の「狐の四天王」や、根岸守信の随筆『耳袋』(文化十一年・1814年)の「悪しき戯致すまじき事附悪事にも頓智の事物」にも同種の話が見えるとしながら、「今日のサゲは、後になって付加されたものだろうと記しています。
私は最初は例によって、偕成社「少年少女名作落語」で読みました。それから数年後に現・三遊亭鳳楽師演(二ツ目で楽松時代)を聴きました。同じ年に八代目・春風亭小柳枝演も聴きました。(その時は春風亭扇昇ていう名でその数ヶ月後に廃業し出家しました。)
その後、テレビ、ラジオ、CD等を通じて、五代目・古今亭志ん生師、八代目・春風亭柳枝師、八代目・三笑亭可楽師、六代目・三遊亭圓生師、六代目・春風亭柳橋先生、三笑亭夢楽師、五代目・三遊亭圓楽師、三代目・古今亭志ん朝師、十代目・柳家小三治師、現・金原亭伯楽師で聴きました。
登場人物の色分けの面白さでは私としては三笑亭夢楽師が印象深いですね。先達の吉兵衛さんと他の若い連中の対比、長屋のおかみさんたちにしても年配のおかみさんと若いおかみさんの色分けが師ならではでしたね。 十代目・小三治師演は亭主が生きていたことを知ったおかみさんたちの袖で頭を隠す仕草がかわいらしかった。
「大山詣り」は結構「火消し」の人が来ていたようですね。

大山は雨乞いや五穀豊穣、商売繁盛にご利益があるとされていて、雨を降らせてくれる山として江戸っ子に信仰されてきたそうです。 火事を消すのにやはり水は欠かせませんからね。 これは大山が急な斜面であるという地形も関連しているそうですね。夏になると相模湾から山に向かって暖かく湿度の高い南風が吹いてくる、その風が急峻な大山にぶつかって上昇気流がおきる、上空で冷やされた暖かい空気は空気は雨雲へと変化する。つまり大山は雨雲を作りやすい山なのだそうで。 昔の錦絵にも大山には当然のつきもののように雨雲が描かれているそうです。https://kitahon.jp/cms/wp-content/uploads/2023/07/%E7%9B%B8%E6%A8%A1%E5%9B%BD%E5%A4%A7%E9%9A%85%E9%83%A1%E5%A4%A7%E5%B1%B1%E5%AF%BA%E9%9B%A8%E9%99%8D%E7%A5%9E%E7%A4%BE%E7%9C%9F%E6%99%AF.jpg 雲を呼び雨をもたらすことで江戸の町を守ってくれる大山は江戸っ子特に「火消し」の人たちから人気が高かったそうです。 「火事とけんか」は「江戸の華」とも言われた江戸時代において、「火消し」は「粋でいなせ」を象徴する存在だったようです。 それ故に「大山詣り」も「粋でいなせ」の最先端だったようですね。 現代で言うなら「人気タレントの店に行きたがる」のと同じ感覚だったようです。
納め太刀は大山詣りの際に奉納される太刀で、武運長久を祈願する意味がありました。
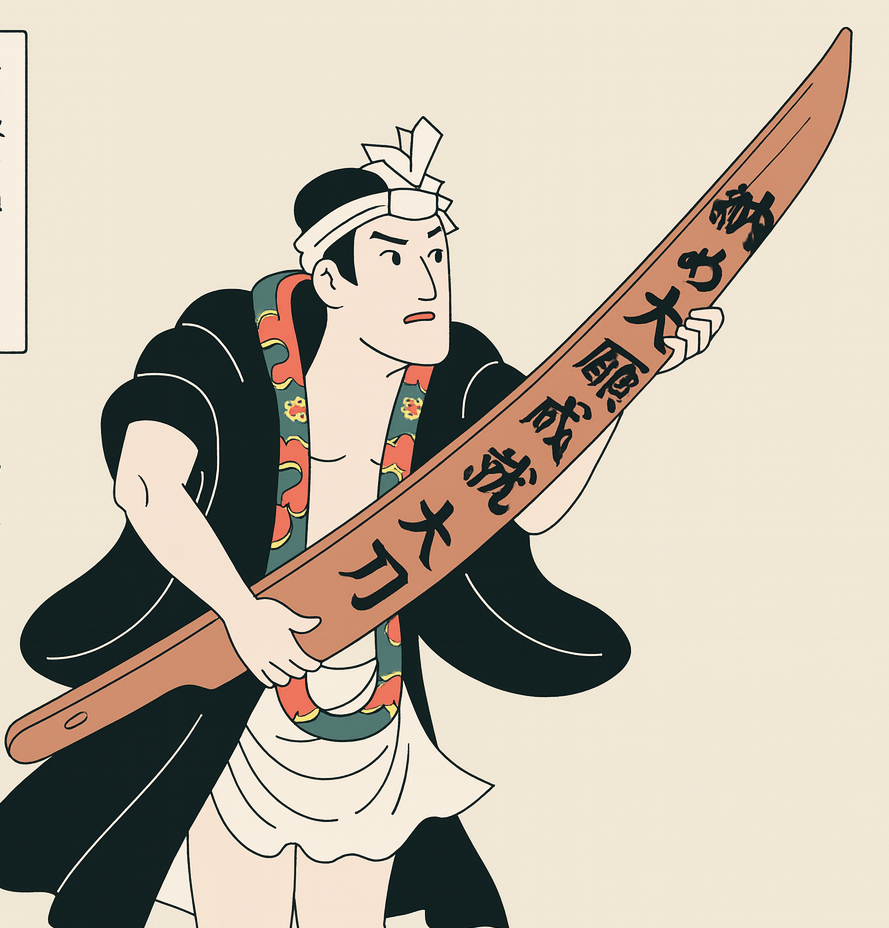
大山詣りの目的地の一つが大山山頂にある阿夫利神社です。https://tabi.jtb.or.jp/v1/storage/res/140020/140020_01C042.jpg
大山の頂上にある神社までの急峻な道を昔の江戸っ子は徒歩で行ったわけですね。 昭和6年よりは麓からケーブルカーが出ているようですが
参拝を無事に終えて江ノ島・鎌倉を観光する楽しみも伴っていたようで。
https://www.photolibrary.jp/mhd7/img383/450-2015022612002820028.jpg
落語の「大山詣り」はその帰り道での間違いだったわけですが、「粋でいなせ」とはやや言い難い展開のようですね。
なんて偉そうなウンチクを並べてきましたが私はまだ大山へ行ったことはなくて。
身体の利くうちに行ってみたいですな。
昔は夏にしか行けなかったようですけど、ネットでみたら秋の紅葉もきれいでした。
https://tanzawa-oyama.jp/assets/img/common/pt-main-know_highlights@2x.jpg


コメント
中国明代(1368年~1644年)の浮白斎主人著「雅謔」のうち「朱搭戸」が狂言「六人僧」の原話だと思います。
朱という男が宝積寺という景色の良い寺へ一同を引き連れて案内します。
皆で酒盛りをして朱は酷く酔っ払ってしまいます。
皆はこれ幸いと朱を残して寺を引き上げて舟に乗って帰ろうとします。
しかし朱は寝てはいませんでした。別の舟で先回りをして村へ帰ります。その際に村人たちをだまそうと全身をずぶ濡れに濡らし、
「大変なことが起こった・帰りの舟がひっくり返ってしまった。俺だけは命からがら助かって帰ってきたが、皆はどうなったのか知らん!」
そう告げたから村中大騒ぎになって……
という話です。
「六人僧」も恐らくここからヒントを得たのでしょう。
圓喬も『百人坊主』の演題で速記を残してます。
https://ameblo.jp/tachibanaya-dasoku/entry-12770224563.html
立花家蛇足さん
コメントありがとうございます。
もともとは中国の話だったのですね。
確か「饅頭怖い」もそうでしたね。
髪がないのは首がないのに劣る
坊主にされるのはそのくらい屈辱的だったのですね。
ひとつテレビドラマのことを書き忘れました~
志田未来主演の「下山メシ」で、ハイキング途中に噺家に出会います。
自分は前座の落語家で、今度師匠の前で『大山詣り』を演るので、一度くらい登山を経験しておこうと……、という会話でした。
しかし、前座に『大山詣り』を教える師匠って、どうなのよ!? と思った次第です(^^)
立花家蛇足さん
ありがとうございます。
入門してから何年か経っている前座さんなんでしょうね。
将来のために「大山詣り」みたいなネタも今のうちに覚えておこうという。
四代目・三遊亭圓馬師はかなり幼い時から二代目・三遊亭圓馬師に入門して、「将来演るようになるから。」と結構大ネタも早くから仕込まれたようですが、これも後になって役に立ったと生前語ってましたね。