あと数日で今年の桜とも……‥と思いながら近所のスーパーにぶらりと寄ると柏餅が出回り始めていました。

年齢を重ねる毎に歳月の流れが速く感じられます。
あとひと月もしないうちにゴールデンウイークに入るわけですね。
五月の落語で私的に想い浮かぶのが
「五月幟」です。
熊さん夫婦の男の子の初節句だが、熊さんは大酒飲みで祝い事をする金もない。
見かねた叔父さんが人形でも買って祝ってやれとかみさんにこっそりと金を渡した。
これを横目で見ていた熊さんが、「おれが人形を買って来る」と言い出す。かみさんは金を渡せば飲んじまうので駄目だと言うが、熊さんは「叔父さんから人形を買えと預かった金だから、絶対に飲んだりはしない」と言って人形を買いに行く。
途中、料理屋の二階から「熊兄ィ」と声が掛かる。通り過ぎようとするが若い者の喧嘩の手打ちでどうしても中に入って手打ちを仕切り、説教の一つでも言ってくれと離さない。
熊さんは断り切れずに二階に上がる。そうなれば先は見えてる。「今日は飲まない」が、「じゃあ、一杯だけ」になり、「まあ兄ィ、そう言わずに駆けつけ三杯と言うから」で、さらに飲み続けべれべれに酔って、懐(ふところ)から人形を買うはずの金を出して気前よく、「勘定の足しにしてくれ」と見栄を張り、若い者たちに見送られて家に帰って来た。
かみさんはいつもの熊さんのていたらくに涙ながらに、子どもを連れて出て行くなんて言い始めた。ばつが悪くなった熊さんはすごすごと二階へ上がって寝てしまった。
しばらくしておじさんが様子を見に来る。かみさんから人形を買うはずの金で飲んでしまったと聞いたおじさんは、今日こそは懲らしめてやると二階へ上がる。
おじさん 「こら、熊、起きろ、何だって人形を買う金で飲んじまうんだ」
熊さん 「いえ、おじさん、人形や幟(のぼり)がちゃんと買ってあります」
おじさん 「どこにある?」
熊さん 「おじさんが、梯子をトントンと上っておいでなすった。これが初幟(上り)だ」
おじさん 「人を馬鹿にするな」

熊さん 「あっしが酒に酔って真っ赤になった金太郎で、酔いがさめたら鐘馗(正気)になりまさぁねえ。この通り人形がございましょ。もう、決して酒、博打はいたしません。勝負事は断ちます。菖蒲太刀(勝負断ちで」
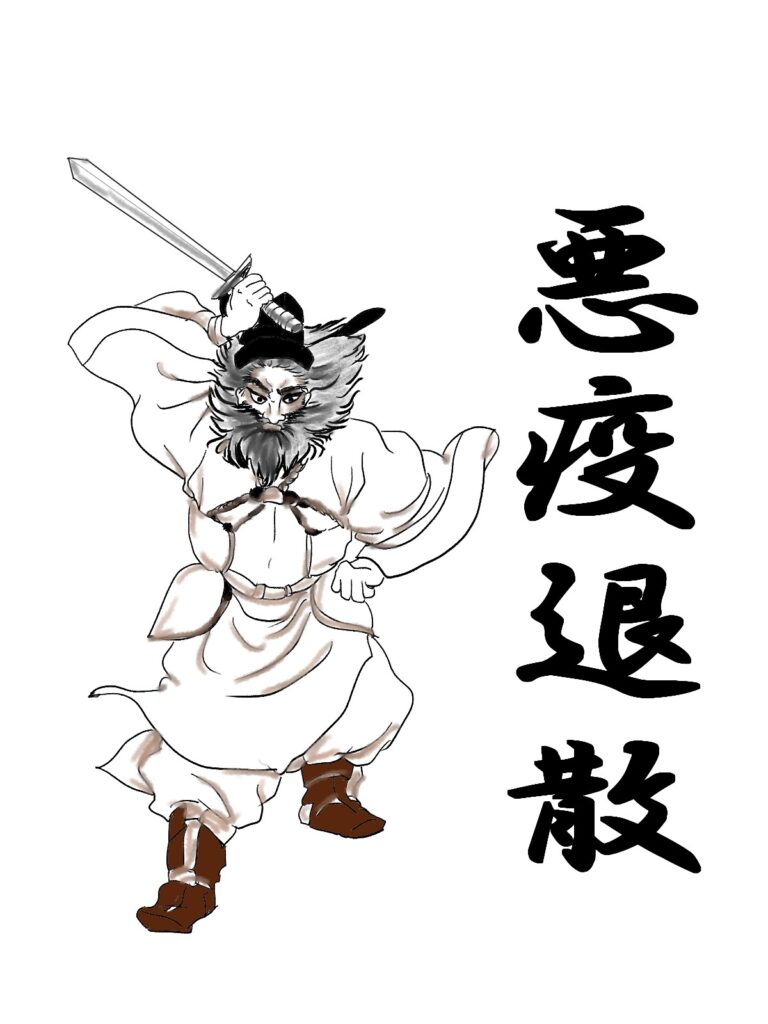
おじさん 「呆れた野郎だ」
熊さん 「おじさん、柏餅を御馳走しましょう」
おじさん 「そんな物、どこにある」
熊さん 「この五布(いつぬの)布団にくるまったところが柏餅、”まろび寝の 我は布団の柏餅 かわいと言うて さすり手もなし”、頭の出ているのはあんこがはみ出したところ、おじさんなめてごらんなさい」
おじさん 「てめえがそう言うなら、俺も一つ祝ってやろう」
熊さん 「大きな声だな、おじさん」
おじさん 「この声(鯉)を吹き流しにしろ」
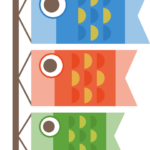
柳派の落語家さんたちによって演じられているとのことですが、私は四代目・三遊亭圓彌師、現・三遊亭鳳楽師で聴いてます。
現・鳳楽師演はNHKラジオで聴きましたが、四代目・圓彌師演は「NHK東京落語会」にてナマで聴きました。
四代目・圓彌師はNHKテレビ「お好み演芸会」の大喜利で「幻の噺家」というキャッチフレーズでお馴染みでしたが、この日の師からは霞が関のオフィス街の中のイイノホールという現代的な大きな舞台に上野、浅草の昔ながらの寄席の空気を運んできてくれた落語家さんという感じを受けました。 「季節感」「粋」という空気でした。噺の中で主人公の熊さんが周りから無理やり酒をすすめられて飲む件においては、「五月幟」という噺を初めて聴く私は「おいおい大丈夫かな?」という気持ちで見てました。 と同時に落語で「酒」を飲む仕草ってこうやるんだと勉強(?)させて頂きました。 酔いの回った熊さんが「『鰹』はやはり生姜で喰わせてもらいてえなあ。」と肴を味わう件には季節感がありましたね。 十歳の頃まで生魚は苦手で、十一、ニ歳の頃からようやく刺身や鮨を「美味い美味い。」と味わえるようになった私は、それまで「鰹」という魚を「刺身」のネタとして意識したことがなかったのですが四代目・圓彌師の高座を観て「『鰹』の刺身はどんなだか食べてみたい。」なんて思いにかられました。

「鰹」の話になるとまた色々長くなりそうなのでまた別の機会に取り上げることにいたします。
マクラではある菖蒲売りがそそっかしい侍に絡まれる小噺を入れてましたね。

ある菖蒲売りがが「菖蒲、菖蒲、仙檀菖蒲」と売り歩くと、そそっかしい侍が「勝負とあらばお相手いたそう」と飛び出した。 これが口達者な菖蒲売りで、少しもあわてず、仙檀菖蒲のいわれを口にまかせて述べたてる。
「女は田の神の奉仕者として田植えの先立つ五月の節句の前の四日夜、定まった家に籠もって物忌みの生活に入ります。そのとき菖蒲を屋根にふくのは、忌籠りの印だったが、菖蒲は邪気を払い、疫病を除き、蛇や虫の毒を避けるのに効果があるというので、どこの家でも菖蒲をふくようになったのです」
「ふうむ……なかなかもって下へはおけぬ」
「それで屋根へ上げます」
「五月幟」は主に柳派の落語家さんたちによって伝えられているとのことですが、私は上記の三遊派の落語家さんでしか聞いたことはありません。 というよりほかの古典落語ほど演じられてない噺ではないでしょうか。 是非後世に残ってほしい噺の一つであるのですが。
今夜は鰹で一杯飲みますが、飲みすぎないように注意します。 酔っぱらって「柏餅」を食べようとしたら布団に包まっている熊五郎さんだったなんてことがないようにします。




コメント
柏餅で寝る、真景累ヶ淵の豊志賀と新吉の会話に出て来ます。
豊志賀「お前、新吉さんそっちへ行って柏餅では寒かないかえ」
新吉「ヘエ、柏餅が一番宜いいんです 以下略
菖蒲売り、四代橘家圓喬の音源が残っている小咄です。✌️
軒菖蒲と菖蒲園さん(hajimeさん)とこの菖蒲とは別物とhajimeさんに伺ったことがあります。
志ん生の『お初徳兵衛』で出世した徳兵衛の船頭姿を表わすのに「当時の船頭は鯔背(いなせ)で、鼠蛇形(ねずみじゃがた)の単衣(ひとえ)に……印伝菖蒲(いんでんしょうぶ)の煙草入れを下げる」と語りました。
圓喬の速記『船徳』でも印伝こそ出て来ませんが、同じような表現で船頭の態(なり)を伝えております。
あたくしも社会人時代は、鞄・財布・ベルト・名刺入れと印伝を使用しておりました。あたくしの場合は菖蒲ではなくひょうたんでしたが。
前回コメントにも出て来ました王子久寿餅(くず餅です)の石鍋商店の近くに印伝の中古専門店もあります。男性ものがあるかどうかは不明です。
たしかシカゴの博物館だったと思いますが、印伝の火消し半纏を展示していたと思います。
立花家蛇足さん
コメントありがとうございます。
四代目・橘家圓喬師の「菖蒲売り」。
是非聴いてみたいですね。
「印伝」は確か昔、「東海道中膝栗毛」に出てきたのを読んだことがありますが、名前の由来は16〜17世紀にインドからオランダを通じて伝わったことからきているそうですね。
話はややズレますが、初代・林家彦六師演の「ちきり伊勢屋」に「べんだら物」という生地の男の着物が出てきますが正しくは「弁柄物」。インドのベンガル地方から伝わったところから来ているそうですね。
シカゴの博物館に印伝の火消しの半纏がありましたか。
「火消し」が世界に誇る江戸の名物ってことですかね。
『菖蒲売り』圓彌さんのを読むと、圓喬というよりは圓遊の『菖蒲売り』に近いように感じました。
いずれにしても絶滅菊落語ですね
立花家蛇足さん
コメントありがとうございます。
四代目・圓彌師は五月の節句にちなんだこういう古い小噺がありますという感じで演じていたと思います。