前回、「雨」に因んだ落語で「笠碁」について記しながら「他になかったかなあ?」と考えてました。
思い浮かんだのが「日和違い」、昭和の新作で四代目・桂米丸師が良く演じていた「相合傘」(古城一兵・作)二代目・桂枝雀師が演じていた「雨乞い源兵衛」(小佐田定雄・作)。 それから「噺」中の「話」で「雨」を扱う「天災」がありますね。 他にもあるのかも知れませんが私の頭に思い浮かんだのはこんなところです。 今回は中でも比較多く語られている「天災」について記して行きたいと思います。
「天災」 あらすじ
ある長屋に住む八五郎は短気で喧嘩っ早い男。

あまりにも酷いため、見かねた隠居に紹介されて、高名な「心学」の先生紅羅坊名丸に診てもらうことになる。
名丸先生は最初「短気は損気」「堪忍袋は破れたら縫え」と格言を言って諭そうとするが、八五郎は一向に感じ入るところがない。 そこで今度はたとえ話として、道を歩いていて店の小僧に打ち水をひっかけられた場合、屋根瓦が風で落ちてきて頭に当たった場合などに、お前はどうするかと尋ねる。

いずれの場合も、八五郎は水を掛けた小僧を張り倒し店の主人に怒鳴り込む、瓦の家の家主や大家に怒鳴り込むと乱暴な回答をする。

それを受けて先生は、今度は傘も雨宿りの場所もない所でにわか雨を降られて全身が濡れたら、天を相手に喧嘩をなされるかと尋ねる。 それに八五郎はさすがに天とは喧嘩できないと答える。
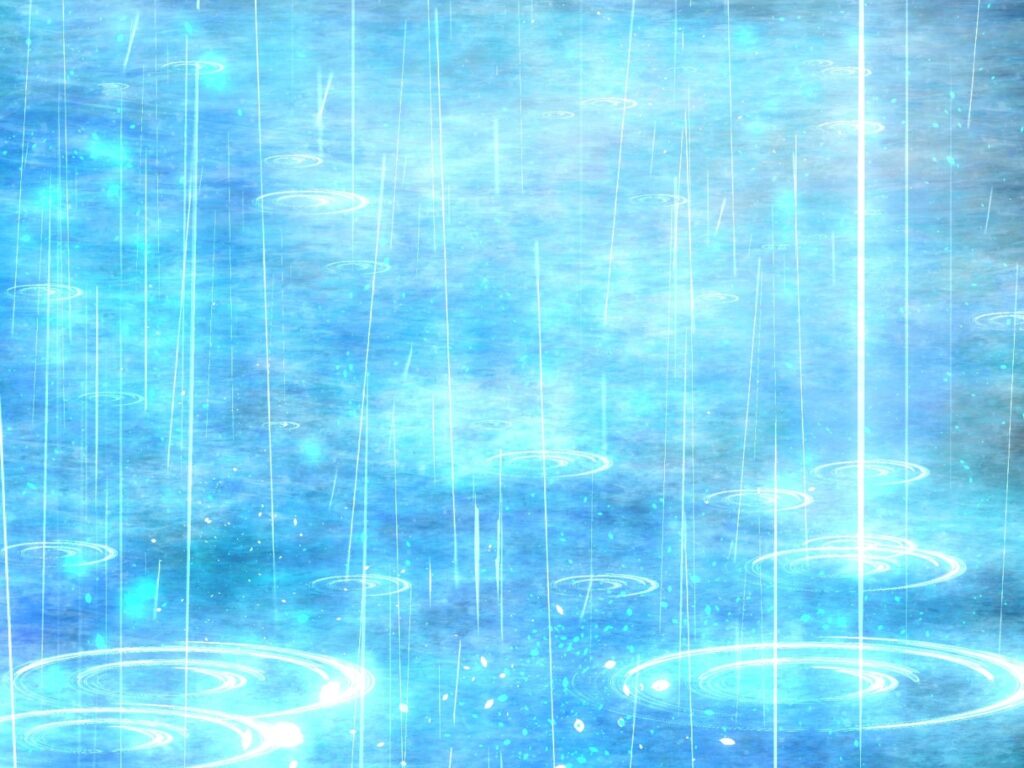
ここで先生は心学では、天がもたらした災いを「天災」と呼ぶこと、今後は水を掛けられたり、瓦が頭に落ちても天のしたことと思って諦めなさいと諭され、八五郎は感心し、納得する。
八五郎が長屋に返ってくると同じ長屋に住む友人が何やら揉めている。 話を聞くと、家に女を連れ込んだところ、別れた女房が戻ってきてトラブルになっているという。 八五郎はさっそく先程得た知識で友人を諭してやろうと考え、まず心学の格言を言おうとするが、うろ覚えで「タヌキはタヌキ」「ずた袋は破れたら縫え」などと言ってしまう。 当然、友人にそっけない態度を取られると、今度はたとえ話だと言って、先の天災の説話を行い、天災と思って諦めろと諭す。 これに友人は答える。 「うちのは先妻(センサイ)だ」
最初は「落語百選」三省堂書店に林家彦六師演と六代目・春風亭柳橋先生演を混合したのが掲載されていたのを読みました。 それから、十代目・柳家小三治師演、五代目・春風亭柳朝師演をナマで聴き、六代目・柳橋先生演、彦六師演、五代目・柳家小さん師演をTVやCDで聴きました。
六代目・柳橋先生は春風駘蕩な持ち味で心学者・紅羅坊名丸を表現し、ガサツ者の八五郎とのやり取りを楽しく聞かせてくれてましたね。 故・川戸貞吉氏は春風駘蕩な六代目・柳橋先生演のイメージが強かった故に、五代目・小さん師演で回答に詰まった八五郎に対して「おいっ!!!」と気合を入れる演出には驚いたと記してました。
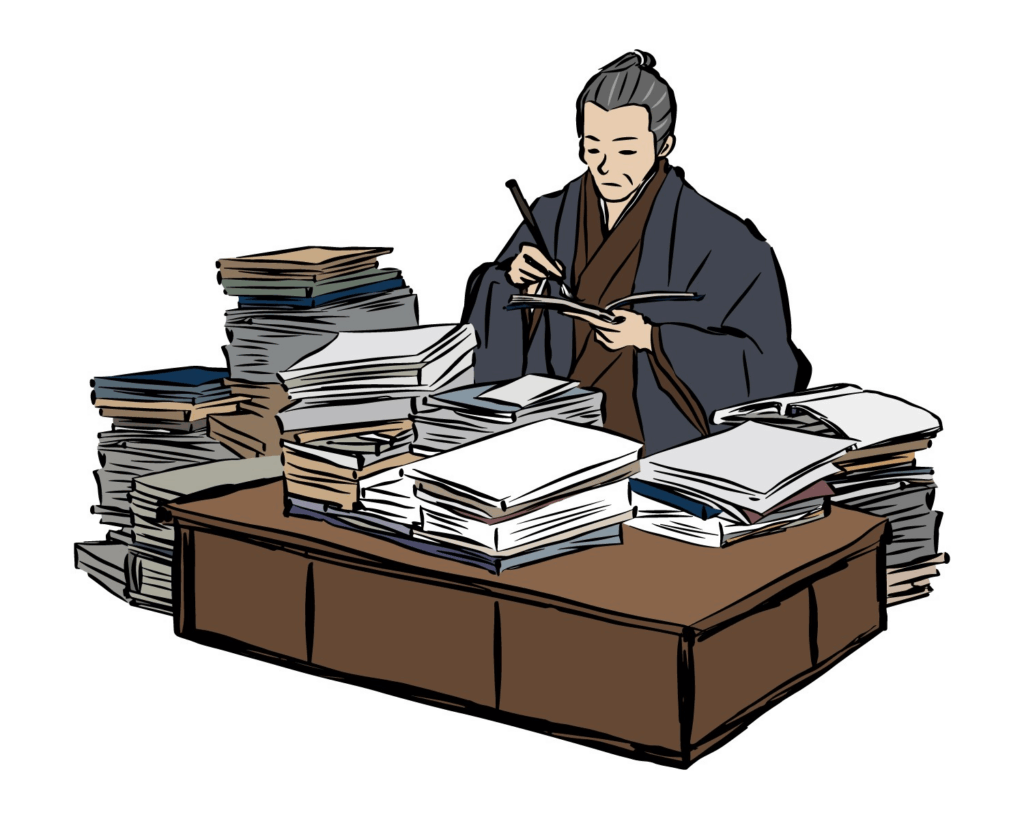
私が最初に聴いた十代目・小三治師演は八五郎と名丸先生の対比の面白さと独自の間の取り方で爆笑を誘ってました。 広い原っぱで大雨に振られて誰を相手に喧嘩をするか考えつつ、上を見て返答に困る態の可笑しさも忘れられません。 五代目・柳朝師演はその件で、「粋な年増の姐さんが傘をさして現れて『お兄さん良かったら一緒に入っていかない?』『そんなことして姐さんの片袖が濡れやしないかい?』『かまわないわよ。何なら二人でどこかで濡れて行きましょうよ。』と二人仲良く相合傘でスーっと行ったときに焼きもち焼くなこのジジイ。」とやり返したり、「広い原っぱだ。『木』は一本もない。」と名丸先生に振られた八五郎が「一本ぐれえあったっていいじゃねえか!そんな原っぱがどこにあるんでえ。」と思わず泣きが入ってしまうのも師ならではの可笑しさでしたね。

彦六師演で「お前さんはこの原っぱの主かい?」と喰ってかかるのも面白かった。
関西では二代目・桂ざこば師が演じていたようですが残念ながら私は聞けてません。
長屋に戻った八五郎が夫婦喧嘩した友人に対して名丸先生の調子を真似て意見する件も最高に面白いですね。「あなたは大変『タヌキ(短気)』と見えますな。」「『堪忍』の袋を常に『頭陀袋』」等々。その件で私が一番可笑しかったのは「夏の雨は馬の背を分ける。」を言い違えて「夏の雨は馬が降らあ。」とやってしまうところですね。
私的にはいつ聞いても笑えるクスグリですが
それに関して、数十年前に読んだ漫画を思い出しました。
吉田戦車先生の「伝染(うつ)るんです」という4コマ漫画でした。
ある家庭の奥さんが外出して「コサメだわ。」と傘をさす。
空からは鮒ぐらいの大きさの「小さな鮫」が降ってきて、そのうち一匹が奥さんの頰に食い付く。
奥さんはそれをヤブ蚊の如く叩き潰す。
これが八五郎の勘違いの通り、「馬」が降ってきたらどうでしょう。
歩いている人はみんな蹴飛ばされて・・・・・。
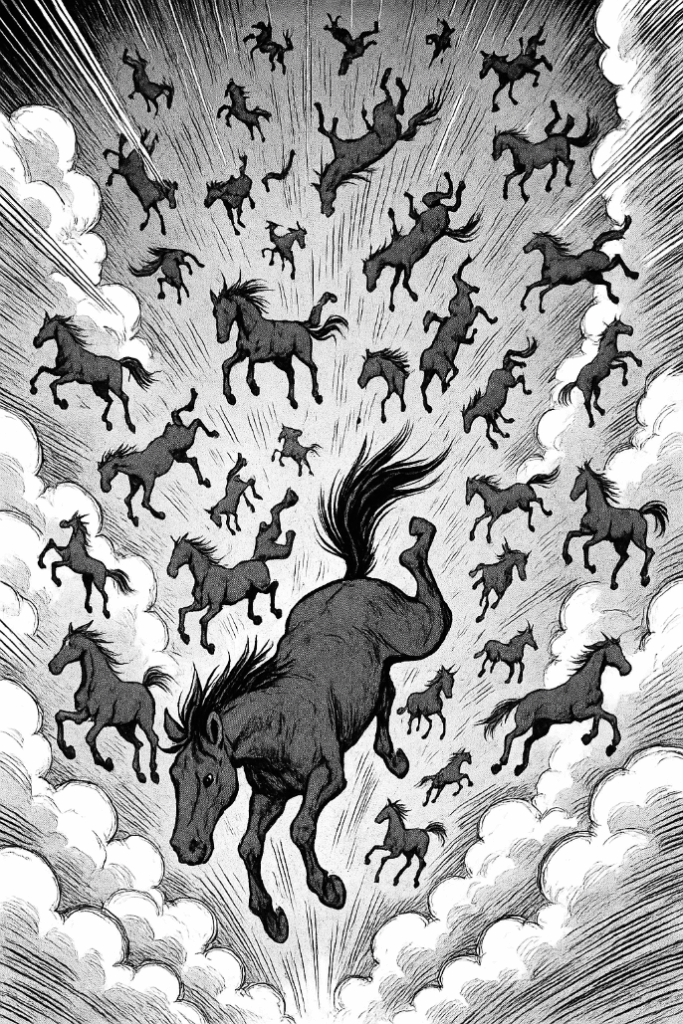
「馬」ならまだしも「犀」が降ってきて、みんな鋭い角で突かれたら・・・・・。
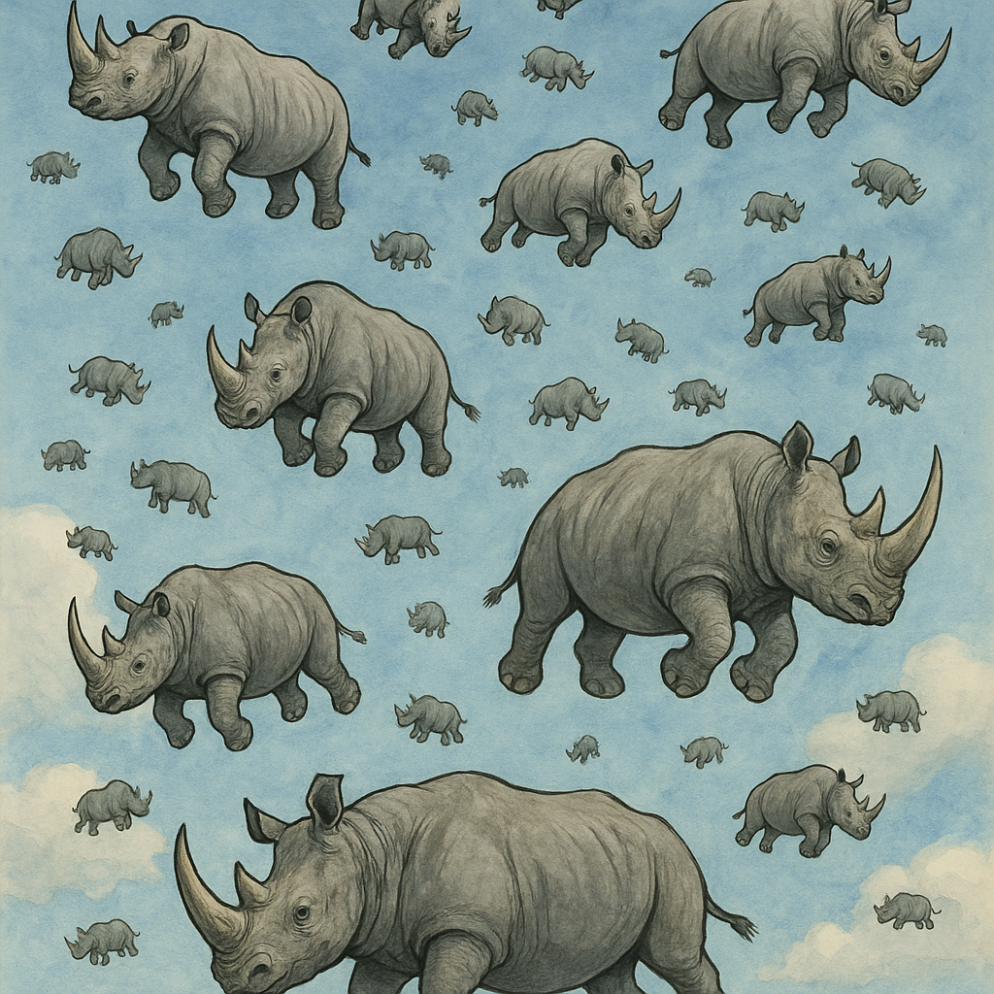
これが本当の「天犀(災)」←これが言いたかっただけだったりして(-_-;)
「付け焼き刃」「鵜の真似をする烏」を笑った噺は数ありますが、中でも「学識ある人」「物知り」の口調を真似てしくじり、「笑い」の対象になる噺は「天災」の他に「二十四孝」「猫久」「茶釜の喧嘩」等がありますね。
その辺の噺もまた取り上げてみようと思います。
今日は五月晴れかなと思っていたら、また雲行きがなんだか・・・・・・。これも「天災」だなって言ったら抗議受けそう・・・・米価の高騰に国民からぼやきが盛んに上がっている時に言うべき言葉ではないかも知れない。
天気なんて簡単に読めるものではないです。二代目・桂枝雀師が「雨乞い源兵衛」の中で語っていたように「『気象庁』のソフトボール大会が『雨』で中止になることだってあるんでございます。」

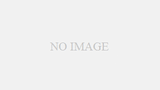
コメント
「雨」で真っ先に浮かんだのはやはり『天災』でした。
あたくしにとっては五代小さんの印象が強い噺です。
志ん生の『雨の将棋』は、不足した王将の代わりに死んだ油虫を使いますが、生き返ってどこかへいなくなってしまうなど、笑いも多い噺ですが音源が病後のものだけに少々残念です。
直接のrainではないのですが、『煮売り屋』の村雨だとか軒雨etc.もありました。
また『中村仲蔵』で仲蔵の開眼に繋がる、蕎麦屋での雨宿りですかね。
付け焼き刃、そのものずばり圓喬の速記には『附焼歯』という小咄があります。
足非(いわゆるびっこ)を扱ってますので、絶滅落語でしょうね。
https://ameblo.jp/tachibanaya-dasoku/entry-12744646780.html
立花家蛇足さん
いつもコメントありがとうございます。
> 音源が病後のもの
五代目・古今亭志ん生師の音源で病後のもので残念だなと思う噺に「怪談牡丹燈籠~刀屋」がありますね。
「お露新三郎」「お札はがし」はかなり元気な頃の音源があります。 長編の導入部である「刀屋」のCDを聴いたにですが病後の録音で何を言っているのかほとんどわからなかったですね。 「怪談牡丹燈籠~刀屋」のCDは桂歌丸師演がCDで市販されてますね。
> 『中村仲蔵』
うっかり忘れてました。
神様に願掛けて俄かに「雨」に降られ、近くの蕎麦屋に駆け込むと、後からずぶ濡れになった「侍」が後から駆け込んできて……というのが大事なヤマ場ですからね。 歌舞伎好きの私が忘れていたのはうかつでした。
> 村雨
五代目・柳家小さん師演「二人旅」で最初に聴きましたが私にとっては意表を突かれるクスグリでしたね。
小学生の時に面白くて繰り返し読んだ滝沢馬琴の「八犬伝」のストーリー展開で大事な役割を果たす名刀の名が「村雨丸」。
落語で「村さめ」という「酒」の銘柄を聴いた時はさぞかし、シャキッとした切れ味の「酒」なんだろうなと思いきや‥‥‥‥でしたからね。
それで、私がまた連想したのが「雑排」ですね。
「春雨」の題に対して、
八五郎「船底を。」
隠居「船底を?」
八「ガリガリかじる春のサメ。」
五代目・春風亭柳昇師の語りを思い出す度にニヤリとしてしまいます。
> 『附焼歯』
蛇足さんのブログで読ませていただきますと確かに現代において演じるのは難しいでしょうね。
「しわいや」「片棒」「出来心」などのマクラで振られる「三ぼう」も説明していくには問題ありそうな時代ですからね。