江戸の名物に武士・鰹・大名小路・生鰯・茶店・紫・火消し・錦絵とあるくらい、「鰹」は昔から江戸っ子の好物のようですね。
その割に「鰹」が題材になっているお江戸落語ってあまりないような気がするのですが。

前回取り上げた「五月幟」では主人公が「鰹」を味わう場面はあったのですが、あくまで脇役でしたからね。
「鰹」が主人公といいますと「江戸名物」についてのマクラ噺としてよく下記の噺が振られますね。
「まいどぉ、初鰹持ってきたぜ」 「おう、ありがてぇありがてぇ!」 「銭はいつでもいいぜ。置いてくぜ」 と、気のいい魚屋は次のお得意に行っちまいます。 「おーい、おみつ」 「はーい。あら?」 おかみさんのおみつさんは台所にある初鰹を見て呆れ顔。 「魚屋が初鰹持ってきたんだ。銭を払え!」 「何言ってんだい。おまえさん……。銭をなんてありゃしないよ」 「なにをぅ!?」 「ありゃしないよ!」 強く出た江戸っ子のダンナはおみつさんの逆襲に声も小さくなります。 「じゃぁ、何か入れてくればいいだろ?」 「入れるもんだってありゃしないよ。みんないれちまったんだから」 「おめぇ着てるじゃねぇか」 「そりゃ着てますよ」 「脱げよ」 「やだよ…。自分で食べんじゃないか。自分でお脱ぎよ」 「そうかい? じゃぁ俺、脱ぐよ」 と話はまとまり自分のどてらを質に入れて初鰹を食べまして、次の日に湯屋に行きますと、友だちもやって参ります。 「どうだ? 初鰹食ったかぁ?」 「食った!」 「美味かったか?」 「寒かった。」

三代目・三遊亭金馬師の「たがや」、六代目・春風亭柳橋先生の「二番煎じ」、六代目・三遊亭圓生師の「鼠穴」のマクラにあったのを聴いたことがあります。「初もの」を食べることにとことん拘る江戸っ子の見栄っ張りぶりの可笑しさが伺える噺の一つですね。
しかし、私はこの噺を聞いた時は「?」でした。 「鰹」は夏場の魚なのに食べるために「褞袍」を質に入れたからって「寒かった。」ということはないだろう。 むしろ「涼しい」のでは?でも「初鰹」は現代の暦でいったら3〜5月のものらしいので。 今年の3〜4月はまだ寒い日がありましたからね。 「褞袍」のような温かい衣類を質入れしたら「寒かった。」でしょうね。
江戸っ子は「女房を質に入れても初鰹だけは食う。」などと普段はその女房に頭が上がらないくせに、豪語していたそうです。 しかし初鰹どころか一切れの鰹すら食える庶民は一人もいなかったのが実際のようですね。
杉浦日向子先生によると食膳に「魚類」を載せること自体贅沢なことだったようですからね。
後半になって「鰹」が主役なってくる噺に林家彦六師が演じた「ざこ八」がありますね。
雑穀商の「雑穀八」の一人娘であるおえんとの婚礼を控えていた良之輔は婚礼の日に突然行方をくらましてしまう。 それから10年後、三十両の財産を築いて戻ってきた良之輔は「雑穀八」が潰れていることに気付く。 仲人を務める予定であった武蔵屋の隠居からは、良之輔に逃げられた「雑穀八」では新しい婿を迎えたが、新しい婿は女遊びと米相場で財産を失って自らは病気で死に、残されたおえんは病をうつされた上に家も財産も人手に渡って廃屋で乞食同然の生活をしている、それもこれも全て良之輔が婚礼から逃げたせいだと責め立てられる。 衝撃を受けた良之輔はおえんの元に向かって今までの事を謝罪し、彼女を娶って「雑穀八」を立て直すことを誓う。 良之輔の勤勉な働きの結果、「雑穀八」は再興され、良之輔が捨てた積もりの三十両で投資した米相場も利益を上げ、更にその儲けたお金でおえんに高度な医療を受けさせて元の美しさを取り戻した。 そんなある日、魚屋が「雑穀八」に「鰹」を持ち込んだ。良之輔これを買って店の者に振る舞おうと考えていたが、おえんは「先の仏様の精進日だから魚は買わない」と断ってしまう。
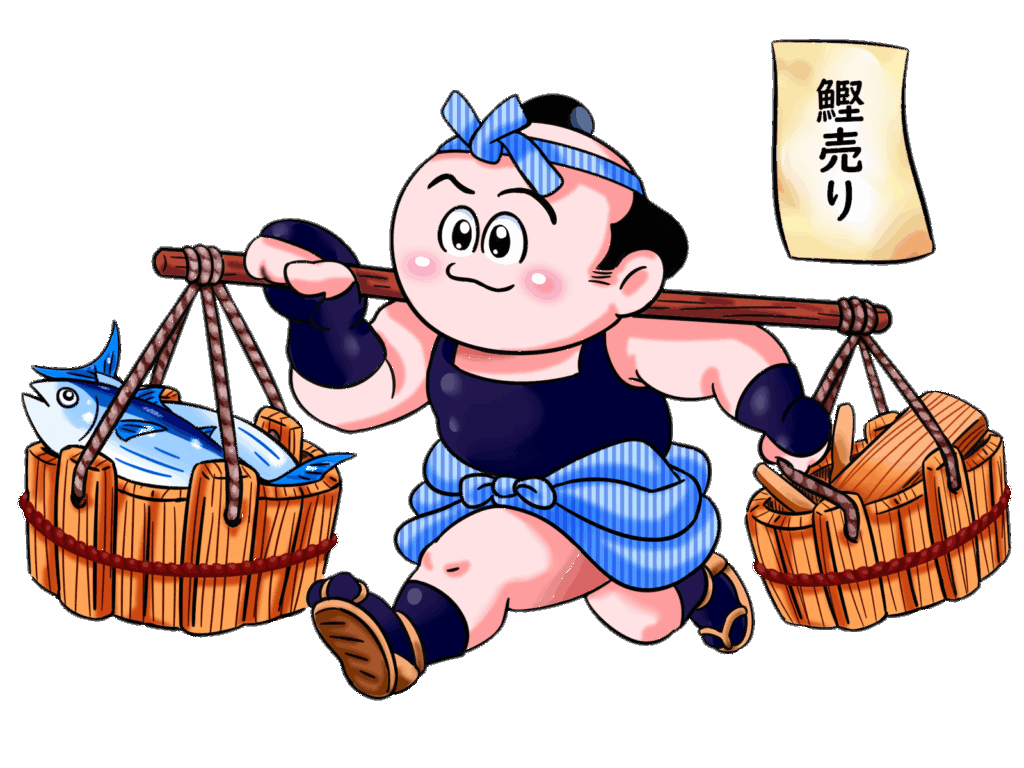
先の仏様の精進日=「雑穀八」を潰した亡くなった婿の命日だと気付いた良之輔は納得せずに夫婦喧嘩を始めてしまう。 事情を察した魚屋がおえんに「おかみさんが先の仏様のことばかり言っているので、今の仏様が腹ア立てる。」
三代目・桂三木助師や六代目・笑福亭松鶴師は夫婦喧嘩の原因となる魚を「鯛」にしてますが彦六師は江戸前に「初鰹」で演じてました。
彦六師の噺の中で「雑穀八」の女将となったおえんが月に三回はどんなに「魚」の嫌いな奉公人でも膳に「焼き魚」を付けていると言ってます。「鰹」や「鯛」に「魚類」のおかずがいかに贅沢であったか伺いしれますね。 また出入りの魚屋も「あっしらのような魚屋がこの鰹仕入れるのは生命がけだよ。『べらぼうめ、(この鰹は)俺が買ったんだ!どうしても持って行く先があるんをだ。譲ってくれなきゃ出刃包丁研ぎ直す。』と向こう気を強くしねえとこいつは手に入らねえんですよ。」と言ってます。 多分 誇張もあるかとは思いますが。 「鰹」という「魚」が江戸時代に日本橋や芝浜の魚市場にどれだけ出回っていたかは勉強不足でわかりせんが、おそらくは「競り」と「喧嘩」のギリギリのラインで勝負して仕入れてくるのかも知れない「魚屋」さんの苦労を考えると「鰹」に限らず「魚類」が高額な食品になっでしまうのは仕方がない話かなと勝手に思ってしまいます。
文化9(1812)年3月25日に芝浦の魚河岸に入荷した初鰹の数は 全部で17本。 そのうち6本は将軍家てお買い上げ、 3本は料亭八百善が2両一分で買い、残りの8本を魚屋が仕入れ、 そのうち一本を中村歌右衛門が3両で買って、大部屋役者にふるまった、という記録があります。こんな話を聞くと改めて「鰹」は宝石並な「食品」だったのだなと改めて思ってしまいます。 聞き慣れている落語で「鰹」があまり登場しないのも庶民の生活からは程遠かったからですかね「鰹」が主役になる落語には現在は演る落語家さんのない噺で「片身分け」というのがあります。 これは私自身も粗筋のみを知っているだけなのですが。
片身分け あらすじ
口がいやしく「ぜい六」とあだ名の付いた喜六、人が食べていると必ず嗅ぎつけて現れる。鰹を片身下ろしたところへ現れたので、亭主が、「今俺が死んだと言って追い返せ」と女房に命じる。これを聞いた喜六は、 「それでは葬儀社から寺の方へ回ろう」と「鰹」の片身を持ち去ろうとする。 「ちょいと、喜六さん。何するの」 「杖とも柱とも頼む兄貴が死んだのやから、せめて片身(形見)はもろうときます」
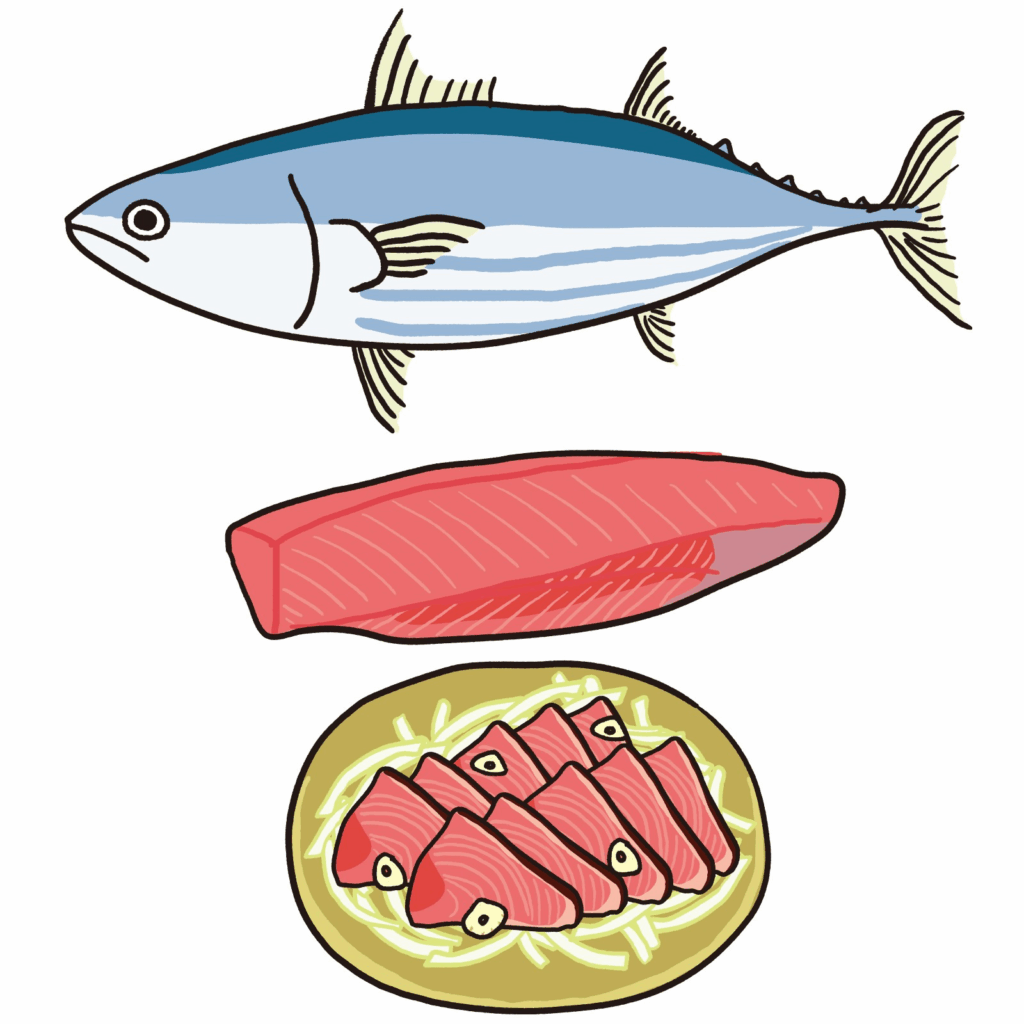
明治時代においては四代目・橘家圓喬師、二代目・三遊亭金馬師、戦後においては八代目・桂文治師が得意にしたそうですね。吉田章一先生は八代目・文治師演を「大阪で修行しただけあって上方者は良く出来ていた。」と評してました。
現代は演じる落語家はいないのでしょうか。 江戸弁と上方弁は使い分けが難しいと言われてますが、マスメマスメディア等で上方弁だけでなく色んな地域の方言に触れる機会は江戸時代・明治・大正時代の数十倍増えていることは私がここに記するまでもないことだし。 噺の内容からして喜六は必ずしも上方者である必要はないと思うし、モデルになりそうな人は結構いるんじゃないかな。 「鰹」の「片身」と「兄貴分」の「形見」を引っかけた「地口落ち」もトボけた感じで面白いと思うのですが。
他に落語というより人情噺の「髪結新三」では「鰹」が金銭問題の掛け合いのアイテムに用いられているようですが、長くなりそうなのでまた次回触れていこうと思います。
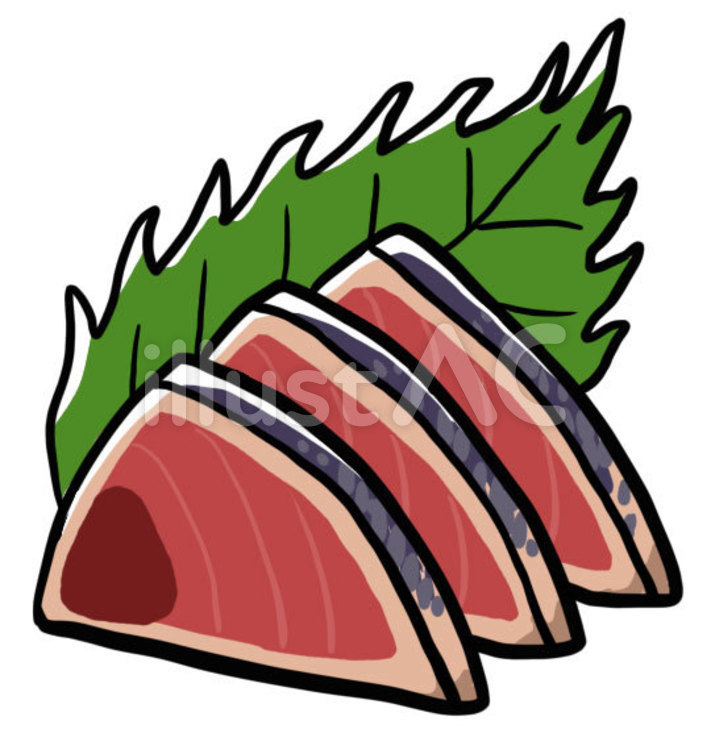

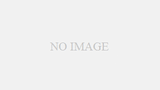
コメント
現在感染症絶賛罹患中でして……。
♪♪ 罹患茶に芝翫茶 ♪♪
リンクのみでご無礼いたします。
圓喬全集 二十二席【片身分(かたみわけ)】
https://ameblo.jp/tachibanaya-dasoku/entry-12762937281.html
立花家蛇足さん。コメントありがとうございます
>そりゃ~絶滅するやろ! という実にくだらない噺です。
生前の林家彦六師の言を借りるなら「邪魔にならない噺」として「片身分け」も演じられないかなと思うのです。
師が得意にしていた「芝居風呂」も「膝前」に出る演者が「主任(トリ)」に出る演者の邪魔にならない噺として演じられていたようです。
「小言念仏」「しわいや」「皮嫌や」「蟇の油」なども邪魔にならない噺ではないでしょうか。
八代目・桂文治師も晩年は比較的、出番は浅かったと聞きます。
浅い出番の短時間の枠で演じられた噺なのではと勝手に思っております。
追記で申し訳ありません。お身体大事になさってください