
「もしかして今年は咲かないのかな?」と心配していたのですが先月末の28日に拙宅の庭の梅の開花がありました。
「梅」と関係した落語といいますと…………ん~ちょっと出てこないな。 「しわいや」は「梅の花」というより「梅干し」の噺だし。
歌がらみでは「質屋蔵」でしょうか。
「質屋蔵」 あらすじ
とある質屋の三番蔵に夜な夜な化け物が出るという噂を、その質屋の旦那が銭湯に行った際にふと耳にする。 それが本当かどうかは分からないが店の信用にかかわる問題だと、旦那は番頭に今夜どんな化け物が出るかを見極めてもらいたいと命じる。
ところがこの番頭、大の化け物嫌い。 そんなことさせられるくらいなら暇を頂戴すると言い出す。
旦那は化け物の正体を「質に取った品物の気」であろうと推測する。
というのも、蔵に眠っている質物のほとんどが、長屋のかみさん連中が亭主の酒代や御飯のおかず代など普段の生活費を切り詰め、苦心惨憺してためたヘソクリで買ったもの。
それをわずかな金のために質入れして請け出せないか運悪く流してしまえば、やはり恨みが質屋へ向くのはやむを得ないからである。
(ここで長屋の女性が、苦労して買った帯を質に入れ、請け出す都合がつかないままに病にかかり、「憎いはあの質屋」という念がこもったまま死ぬ、というたとえ話を、旦那が番頭に延々と聞かせる)
しかし、それでも気味が悪いのはどうしようもない。
そこで旦那、誰か助っ人を頼んで一緒に張り番をしてもらったらと番頭に提案する。
番頭が推薦したのは出入り職人の熊五郎。
旦那も普段から威勢のいい事を言い、何かというと体中の彫り物自慢をする熊さんならと太鼓判。
小僧の定吉を使いにやろうと呼びつけると、定吉「三番蔵のことですか?」
どうやら立ち聞きをしていた様子。
旦那は普段からおしゃべりな定吉をきつく叱り、緘口令を言い渡して使いに出す。
定吉は普段から「おしゃべりだ。おしゃべりだ」と小言を言われ続けているようで、どこかで鬱憤晴らしをしてやろうと思っていたのだが、どうやら今がそのときだと思ったらしい。
熊五郎の家について、旦那が用があるから急いでくるようにと言うついでに、早く行かないと店をしくじる(出入り禁止になる)と付け加える。
その口ぶりから「旦那、怒ってるのか?」と熊五郎が尋ねると、「カンカンになって怒ってる」と、事実を省略して話す定吉。
熊五郎、旦那の怒っている理由を聞き出そうとするのだが、定吉は「タダじゃ嫌だ」と足元を見る。
ならば好きなものを買ってやると言う熊五郎に定吉、
「芋羊羹(もしくは焼き栗)が食べたい」
「売ってたら買ってやる」
「後ろで売ってる」
実は定吉、あらかじめ見当をつけていた。
熊五郎が小さいのを一本買おうとすると、定吉は大きいのを二本買えと言い出す。
熊五郎「そんなに食えないだろうが。」 定吉「一本は普段世話になっている岩どんにやるの。」 「お前、人のもので義理しなくていいの」と大きいのを二本買って定吉に喋らせる熊五郎。 ところが定吉は断片的にしか覚えてなく、何がなんだかさっぱり分からず仕舞い。 挙げ句の果てに定吉はとっとと先に帰ってしまう。 一杯食わされた格好の熊五郎だが、定吉の言った「酒」「おかず」というフレーズに何か引っかかるものがあったよよらしく「あの事がばれたんだ!!」 早速店へ飛ぶようにやってくる。 旦那はイライラ。 実はこれ、熊五郎が遅く来たからなのだが、早合点している熊五郎は言い訳をし始める。 ある日、喉が渇いてお勝手へ水を飲みに行こうとしたとき、片口の中に酒がなみなみと入っているのを見つける。 側 で働いていた女中のお清に訊いてみると座敷から下がってきた燗冷ましの酒で、捨てるか糠味噌の中に少しずつ入れる以外使い道がないと言う。 ならば自分が貰ってもかまわないだろうと思い、お清に断って片口ごと貰って帰り、飲んでみると燗冷ましでありながら普段のより大層美味で、喜んで飲んでいるうちに二日ばかりでなくなってしまう。 翌日、女房に「もう一度ああいううまい酒が飲んでみたい」と言うと、 女房「だったら貰ってくれば?」 熊五郎「自分が飲むからくれなんて言いにくい。」 女房「断るからいけないの。 黙って貰って来ちゃえばいいじゃない」 熊五郎「そんなことできるのか?」 女房「あたしに任せておいて。」 すると、どういう伝を頼ったのか女房が酒を貰ってきてくれたので、燗をして飲んでみたらなおさら美味かった。 それからもちょくちょく貰っていたらしいのだが、あるとき蔵に酒樽が山のように積まれているのを見てお清に理由を訊くと、酒好きの旦那のためにいつもこのくらい用意してあるのだとか。 しかし、いくら酒好きとはいえいっぺんにこんなには飲めるわけもなく、時がたてば味が落ちてしまうだろうし、こっちもちびちび貰うよりもいっぺんに貰ってしまったほうが手っ取り早いと大八車を引っ張ってきて5~6樽もって帰ってしまったという。 これを聞いた旦那、全く知らなかったので「その酒、いまだに探してるよ」というと、熊五郎、また言い訳をし始める。 ある日、御勝手で簡単な普請をしていると、お清がどうもこの辺が片付かないとぼやいているので、熊五郎がすっかり片付けてしまう。 すると、お礼に今夜のおかずにでもと沢庵を二本、荒縄で絡げて渡してくれた。 持って帰って食べてみると、これが普段のより大層美味。 こういう美味い沢庵なら他におかずはいらないと、二日ばかりで平らげてしまう。 翌日……(以下、悪行1と同工異曲)これも知らなかったという旦那。 する と熊五郎、「じゃ、味噌のことで……」 呆れる旦那「そんなこと他の店でやると、手が後ろへ回るよ。」 熊五郎「大丈夫。何か持ち出すのは旦那の家だけですから。」 旦那「勝手に決めるな。」 まあ、それはそれこれはこれと、話を進めることにする。 「熊さん、強いんだってね」と言う旦那に、彫り物自慢を始める熊五郎。 まあ、それはそれこれはこれと、話を進めることにする。 例の話を持ちかける。 すると、途端に熊五郎の態度ががらっと変わってしまう。 そう、人間相手なら腕っぷしの強い熊五郎もまた、化け物や幽霊といった類は苦手だったのだ。 いまさら帰ることも許されず、そのまま時は過ぎてただいまの時刻で夜の十二時時分、いきなり蔵へ入るのも気味悪かろうからと蔵の手前にある離れで、番頭と二人で番をしろと言う旦那。 お清がこさえてくれた夜食の膳を熊五郎が持ち、手燭の明かりを番頭が持ってこわごわ移動する。 気付けに飲もうという熊五郎だが、番頭は酒が飲めない。 やむなく一人、側にあった大きな湯飲みで飲み始めるが、恐怖で感覚が麻痺していて酒の味がさっぱり分からなくなっていた。 「飲めないんだったら、膳の上のものどんどん片付けちゃったほうがいいよ。ことによるとこれがこの世の食いおさめになるかも」 「何でそんな事言うの」 番頭は熊五郎にお願いがあるという。 何だと訊くと、びっくりして腰を抜かしちゃうからお化けが出てもいっぺんに「出た!」と言わずに、「で~」で踏ん張って、番頭が逃げ切った頃に「た~」 「そんな事言えるか」 いよいよ草木も眠る丑三つ時、三番蔵の戸前が光ったかと思うと、ドカ~ン!という大きな物音。
「出た~!」
途端に二人とも腰を抜かしてしまう。
しかし、責任があるので蔵まで這って行き、戸前を開けると中で繰り広げられていたのは、
「かたや~、大紋、大紋~。こなた~、黒龍、黒龍~」
なんと、帯と羽織が相撲をとっているではないか。
実はこの二品の持ち主はある相撲取り。やはり旦那の言うとおり質物の気がお化けになったのだ。
その光景をしばらく無言で見つめていた熊五郎が、
「番頭さん、あれを御覧なさい」
指差すほうを番頭が見ると、藤原さんから質入れされた一幅の掛け軸が下がったかと思うと、中の一本の「梅の枝」を持った菅原道真公が抜け出てきて
「東風吹かばにおいおこせよ梅の花主なしとて春なわすれそ・・・・・・・そちがこの家の番頭か?」
「へへ~」
「藤原方に参り、とくと(急いで)利上げ(質入れ後に払う利息分の支払い)をせよと申し伝えよ。麿もどうやら、また流されそうだ。」
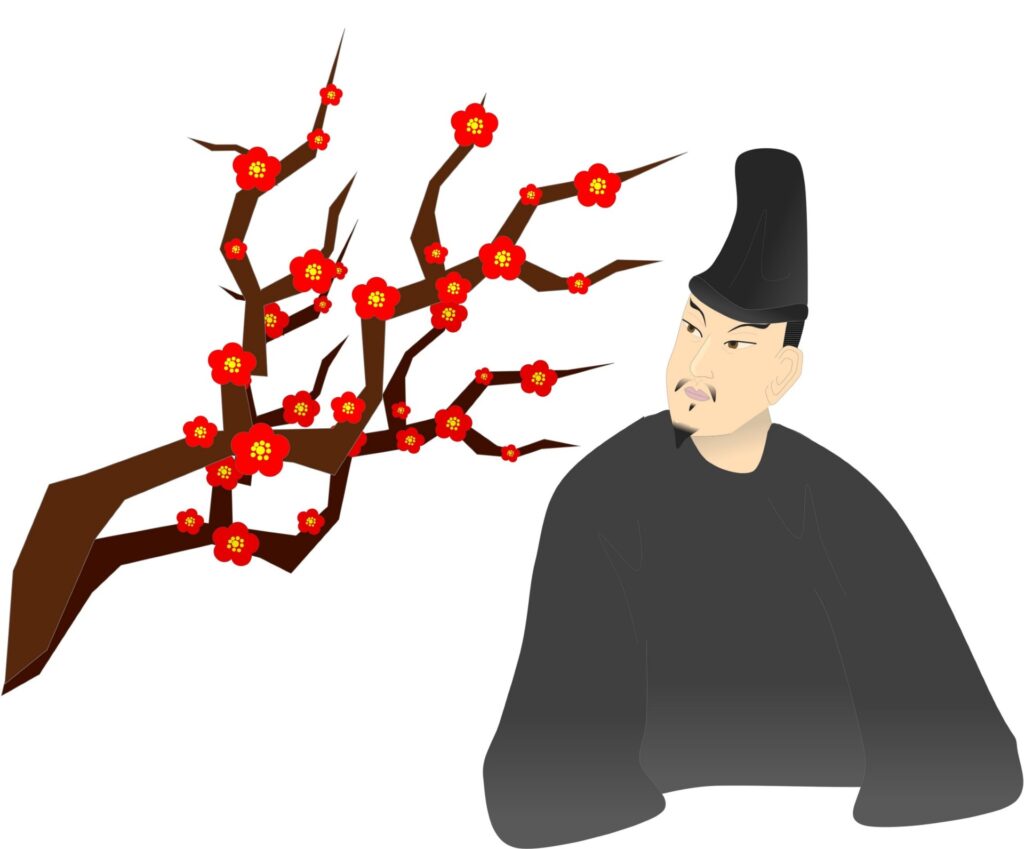
サゲはよく出来ていると思うのですが、現代の客にわかる人がどのくらいいるのでしょうか。 右大臣菅原道真公が左大臣藤原時平公の讒言により、九州の太宰府に流されて、その地で生涯を終えたという話を知っている客がどのくらいいるかですね。 六代目・三遊亭圓生師、四代目・三遊亭圓彌師はに道真公が流された話をマクラでキチンと振って 噺に入ってました。
流されたと言っても大宰権帥(だざいのごんのそち)という役職はあったそうなのですが。 いよいよ都を離れる時に自邸の庭に今を盛りと咲いている「梅」に詠んだ歌が、「東風吹かば匂ひおこせよ梅の花あるじなしとて春な忘れそ(わが家の梅の花よ。東風が吹いたら、私のいる太宰府まで匂いを届けておくれ。主人がいないからと言って、春を忘れてはならないよ。)」
太宰府に移った翌年の春のある朝、庭を見ると「梅の花」が咲いていて、道真公は大変喜んだという。 都の自邸の「梅の木」が主を慕って一晩で飛んで来た。 「松」「桜」はあったがそこに「梅」が飛んで来たので、道真公は「これで『よろし』」と言ったという。 「こういうことは『学問』がないと言えない。」と六代目・圓生師は言ってました。
私はそのへんの学問はまるで無いもので何のことやらわからないのですが。

飛び梅伝説の実際は伊勢国度会(わたらい)の社人である、白太夫という人物が、道真を慕っ て大宰府に下る折、都の道真公の邸宅に立ち寄り、夫人の便りとともに庭の梅を根分けして持ってきたそうですが、道真公は都から取り寄せたことをふせて、「梅が飛んできた」ということにした、ともいわれているようですね。
人形浄瑠璃「菅原伝授手習鑑」でこの場の「筑紫配所の段」が上演されたのを2回観たことがありますが、「梅の木」ではなく忠実な家来の「梅王丸」が都から来るのですね。そして、藤原時平公の命令で道真公の暗殺に来た鷲塚平馬なる男を捕らえる働きをします。

どうしても都に戻れる望みがないとわかると道真公は大変怒り、天拝山に登って三日三晩爪先立ちをしながら祈り、ついに魔界に入り雷神になったという。
このあたりに関しては様々な言い伝えがありますね。 私が別に聞いた話では怒った道真公が天拝山で祈りを捧げると都に雷が落ちて大勢の人が死んだとか。
先述の人形浄瑠璃「菅原伝授手習鑑」では自分を暗殺しようとした平馬の口からの時平公が法皇を押し込めて天下を覆そうとしているという陰謀を聞くと顔色を怒りに変え、「梅の枝」で平馬を打ち据えるとその首が飛んでしまう。
「梅の枝」が恐ろしいアイテムになってしまうのですね。 さらに「魂魄雲居に鳴るいかづち…首領となって眷属を引きつれ、都に上り謀叛の奴ばら引き裂き捨てん」と梅王丸など周囲の者が驚き取り付くのも撥ね退け、突風の吹きすさぶ中でついに天神と化し、天へと昇って行くという。 後の「北嵯峨の段」で道真公の御台所・園生の前の夢であったと分かるわけですが。
五段目「大内天変の段」で藤原時平公は菅原道真公の左遷の責任を取って自害した桜丸、園生の前の命を守って落命した八重の夫婦の怨霊に悩まされ、二人の家来が落雷の直撃を受けて横死するのを目の当たりにする。
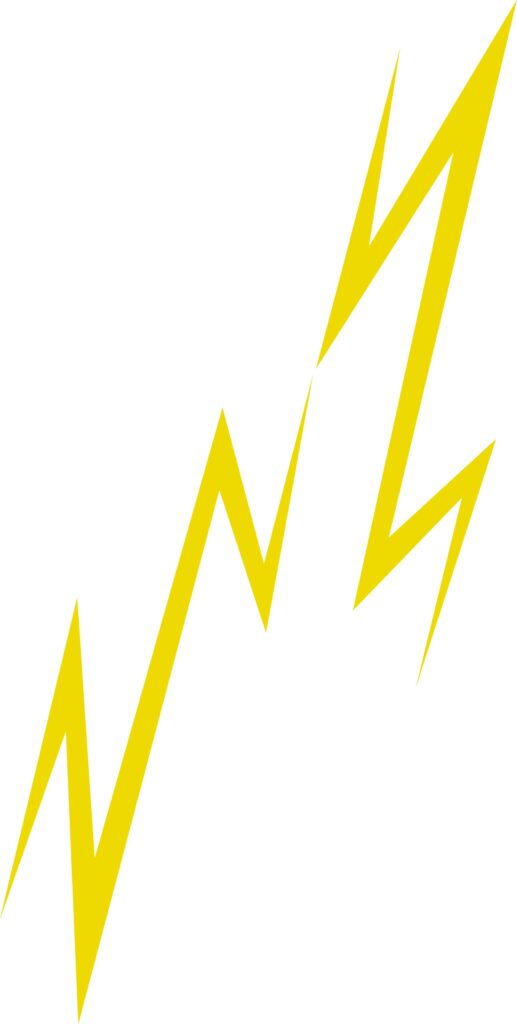
そして自身も道真公の養女苅屋姫、若君菅秀才によって討たれる。 実際の時平公は病死しているそうなのですが、三十九歳という若さだったので菅原道真公の怨霊の仕業ではないかという噂が立ったようですね。
ホラーな伝説や物語のある天神様、菅原道真公ですが、学問の神様として人気の高いことは私が申し上げるまでもありません。
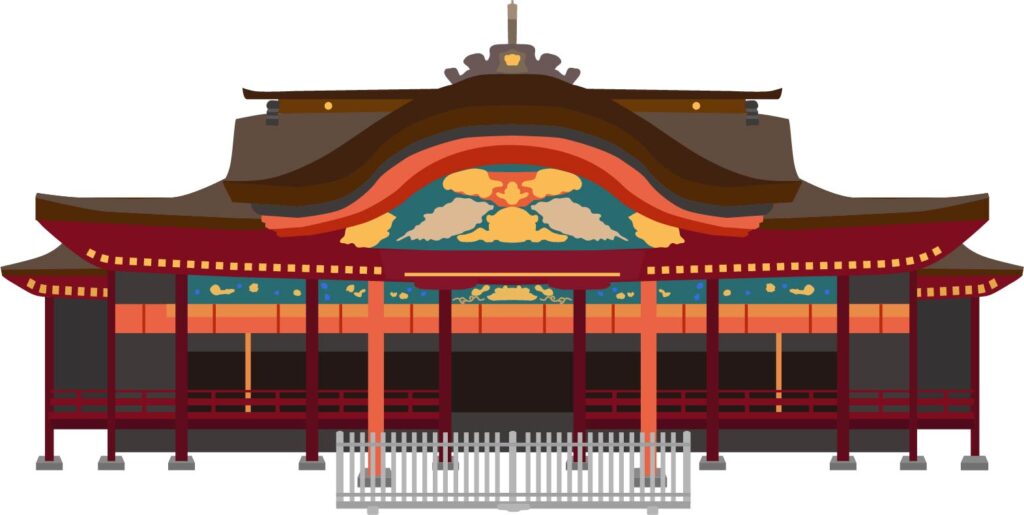
合格発表のシーズンになりましたが、天神様のご利益を授かれた人もかなりいるかな?
「質屋蔵」は噺の性質からして夏の噺のようにも思われますが、三代目・桂米朝師演をよく聞いていると秋の噺なのですね。 小僧定吉が熊五郎に「焼き栗」をねだったりして。
この度は拙宅の庭が今年も「春を忘れずに」花を咲かせてくれたことに因んで「天神様」の噺、「質屋蔵」を取り上げました。 来年も引き続き「春を忘れずに」開花させてくれることを祈って「お開き」とさせていただきます。
としたかったのですが編集しながら「馬鹿に寒いな。」と思ったら、外に雪が。 今時分だったら「初雪」じゃなくて伊勢正三先生やイルカ先生の歌っている通り「なごり雪」って言いたいですね。 「暑さ寒さも彼岸まで」と言いますが皆さんどうかお身体に気を付けて。

。
右
SEO
上に移動下に移動パネルを切り替え: SEOSEOタイトル文字数:0
検索エンジンに表示させたいタイトルを入力してください。記事のタイトルより、こちらに入力したテキストが優先的にタイトルタグ(<title>)に挿入されます。一般的に日本語の場合は、32文字以内が最適とされています。(※ページやインデックスの見出し部分には「記事のタイトル」が利用されます)メタディスクリプション文字数:0
記事の説明を入力してください。日本語では、およそ120文字前後の入力をおすすめします。スマホではそのうちの約50文字が表示されます。こちらに入力したメタディスクリプションはブログカードのスニペット(抜粋文部分)にも利用されます。こちらに入力しない場合は、「抜粋」に入力したものがメタディスクリプションとして挿入されます。メタキーワード
記事に関連するキーワードを,(カンマ)区切りで入力してください。入力しない場合は、カテゴリー名などから自動で設定されます。インデックスしない(noindex)
このページが検索エンジンにインデックスされないようにメタタグを設定します。リンクをフォローしない(nofollow)
検索エンジンがこのページ上のリンクをフォローしないようにメタタグを設定します。詳細設定canonical
ページ内容が類似もしくは重複しているURLが複数存在する場合に、検索エンジンからのページ評価が分散されないよう、正規のURLがどれなのかを検索エンジンに示すために用いる記述です。コンテンツが重複している場合は、正規ページのURLを入力してください。
カスタムCSS
上に移動下に移動パネルを切り替え: カスタムCSS
カスタムJavaScript
上に移動下に移動パネルを切り替え: カスタムJavaScript投稿ブロック
東風吹かば……。

このあたりに関しては様々な言い伝えがありますね。 私が別に聞いた話では怒った道真公が天拝山で祈りを捧げると都に雷が落ちて大勢の人が死んだとか。
先述の人形浄瑠璃「菅原伝授手習鑑」



コメント
梅の花は、なんといっても花の魁ですから……、美しいですよね。
「梅」の噺というと、『雑俳』ですね。
初雪や 梅の足跡 犬の鼻
あれっ!?
初雪や 犬の足跡 梅の花
でしたっけ?
また、『松竹梅』の』本来のサゲも梅の開花にちなんだものですね。
「梅さんのことだ。いまごろは、ひとりでひらいているだろう」
『天災』にも、
手折(たお)らるる 人に薫るや 梅の花
とあります。
本日の東京は寒く、東風どころか北風(圓朝は『文七元結』で「ならい」とルビを振りました)です。
立花家蛇足さん。コメントありがとうございます。
そうですね。歌や俳諧絡みだと「雑俳」もそうですね。
「松竹梅」も「お開き」と記しながら「そう言えば。」と思い出したのですが。
馬鹿に冷え込むなと思ったら外は雪ですからね。
伊勢正三先生やイルカ先生の歌う通り「♪東京で見る雪はこれが最後」にして欲しいです。
寂しそうに呟く彼女は「♪去年よりずっと綺麗になった〜。」なぐらい若くて美しいのでしょうけど、コチラは益々老いていくのですからから。
今夜も温かいものを何か食べて寝ます。