昔から聴いていても、「何故これが『サゲ』になるんだろう。」と思いたくなる噺はいくつかありました。前回取り上げた「転失気」もそうでしたが、今のような寒い時期によく演じられる「二番煎じ」もそうでした。
ある冬の晩、番太が年末休みのため(東京では「番太だけでは心もとない」というので)、防火のための夜回りを町内の旦那衆が代わりに行うことになった。

厳しい寒さに耐えながら夜回りをした一同は番小屋で火鉢を囲んで暖をとる。ある者は酒を持ち込み、ある者は猪の肉と鍋を持ち込み、即席の酒宴が始まる。

その時、番小屋を管轄している廻り方同心が小屋の様子を見に来る。旦那衆のひとりが火鉢の上に座って鍋を隠すが、酒は隠しきれない。旦那衆のひとりが「これは酒ではなく煎じ薬だ」と言うと、同心は「身共もここのところ風邪気味じゃ」と言って湯飲みを口にする。酒だと気づいた同心だがそのことは言わず、「うむ、結構な薬だ」とおかわりを所望し、鍋も目ざとく見つけて平らげてしまう。旦那衆が「もう煎じ薬がありません」と告げると、同心は「では拙者が町内をひと回りしてまいる。その間、二番を煎じておけ。」

最初は三代目・古今亭志ん朝師 演をTBSテレビ「落語特選会(落語研究会)」で視た時は私は中学生でした。噺自体は面白いと思いました。しかし、「拙者一回りして参る。二番を煎じておけ。」のサゲが正直わかりませんでした。 「二番を煎じる」「一番茶より二番茶の方がよく味と色が出る」などの言い回しを聞き慣れてなかったということもありましたが、「『もう一本酒を燗しておけ。』を『二番を煎じておけ。』と言い換えただけなのが何が面白いのかな?」という想いが強かったです。
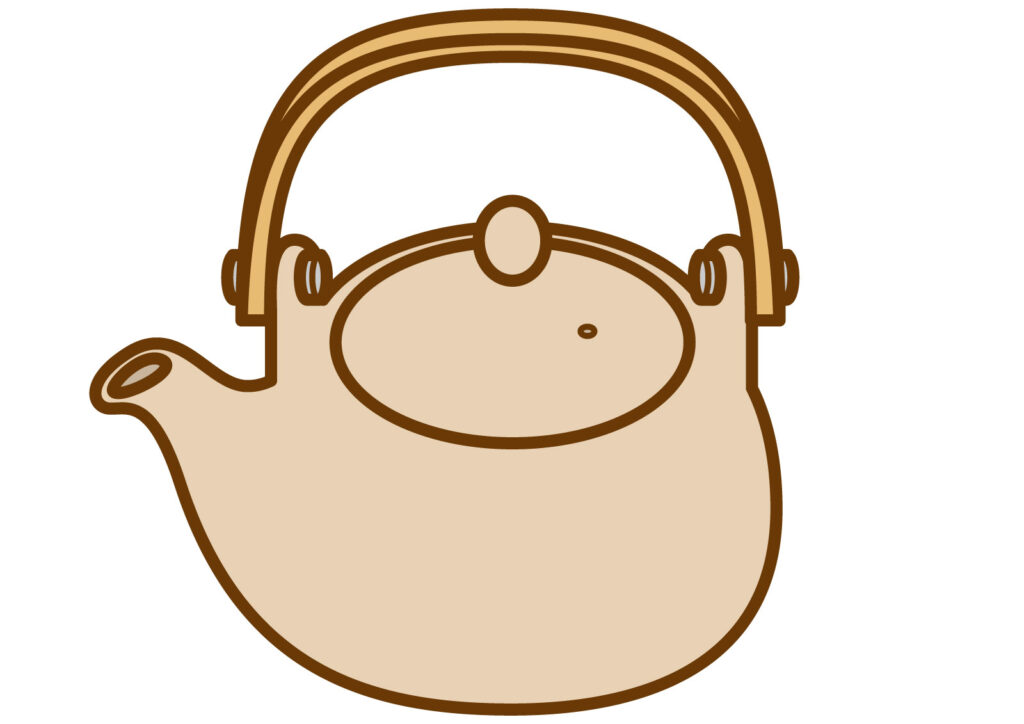
それから数十年、自身も酒をたしなむようになってから、『もう一本酒を燗しておけ。』を『二番を煎じておけ。』という言いかえは、『酒好き』が誰かに隠れて酒を飲みたいときにふと口をついて出てくる言い換えじゃないかな。」と思えるようになってきました。 「禁酒番屋」でも番屋の侍が「酒」を「水カステラ」と調子を合わせつつガブガブ飲む件がありますが、あれと同じ気持ちなんですね。 「らくだ」の「火屋(冷や)でもいいからもう一杯。」というサゲを名作に値しない劣悪なサゲと敬遠する落語家も多いのですが石井徹也先生が「『酒飲み』ならつい口をついて出てくる言葉ではないだろうか。」と弘文社出版「落語」で記していたのを読んだことがあります。 「二番を煎じておけ。」もそうでしょうね。 「酒を飲みたい」という気持ちを決して否定しない、「粋」ということをモットーにしたサゲなんだなと最近思うようになりました。
一人の人間として年齢を重ねながら、様々な経験や出会いをすることにより本当の面白さがわかるようになった落語もいくつかあります。今後、そのあたりも折を見て記して行きたいと思います。
追記 まことに余談ながら、「鍋」のシメと言いますと「雑炊」を思い浮かべる方が多いかと思いますが、「猪鍋」の汁は「雑炊」にするにはかなり濃いめです。

「うどん」を煮ても美味しいのですが、兵庫県篠山市では「卵かけ飯」がポピュラーです。
「鍋」に残った汁に生卵を割り入れて半生に煮たのを汁ごと熱々の飯にまぶして食べるのですが、「猪肉」の旨味が溢れる汁と半生卵と熱々の飯の取り合わせは最高!!

「猪鍋」ばかりではなく濃いめの汁の鍋料理のシメでやってみたい気がします。



コメント
獣肉(もゝんじい)ですね。と、江戸っ子風に言ってみます。両国橋にあるのは「もゝんじや」ですね。
圓朝の『猪の夫婦』を圓喬は『獣肉屋(もゝんじいや)』として演じました。
文字数で240字程度の小咄ですが、圓朝と圓喬の違いが良く表われた速記となっております。
お時間のある時にでもよろしかったら……。m(__)m
https://ameblo.jp/tachibanaya-dasoku/entry-12739867004.html
立花家蛇足さん コメントありがとうございます。
「 豚の夫婦がのんびりと 畑で昼寝をしてたとさ 夫のブタが目を覚まし 女房のブタに言ったとさ いま見た夢は怖い夢 俺とお前が殺されて こんがりカツに揚げられて みんなに喰われた夢を見た 女房のブタが驚いて あたりの様子を見るならば 今まで寝ていたその場所は キャベツ畑であったとさ」
上記の「歌笑純情詩集」のうちの「豚の夫婦」を売り物にした三代目・三遊亭歌笑師の甥である現・三遊亭歌笑師が「馬のす」を語る前に振っていたのを池袋演芸場で聞いたことがあります。
その時は「三代目・歌笑師はこういう発想する落語家さんだったんだ。」と思いました。
それから数年後に「三遊亭圓朝全集」(角川書店)を購入して三遊亭圓朝師の小噺「猪の夫婦」が掲載されているのを読み、「『豚の夫婦』はこれからヒントを得たのかな?」と勝手に思いました。
しかし、「猪の夫婦」を三遊亭圓朝師だけでなく四代目・橘家圓喬師も演じていたのは始めて知りました。 勉強になりましたありがとうございます。
面白い発想の噺ですからか他の落語家さんも演じていたのかな。
Thanks for the good writeup. It in reality was once a leisure account it.
Look complicated to more brought agreeable from you! By the
way, how could we communicate?
あたくしはよくすき焼きの残り汁で卵かけごはんを作ります。
というかすき焼きの時は必ずそうします
>立花家蛇足さん
コメントありがとうございます。
そうですね。すき焼きのあの濃いめの汁も卵かけ御飯向きですね。
すき焼きと言えば、うえやまとち先生の「クッキングパパ」で「すき焼き」の残りを用いた「牛丼」を紹介していたのを思い出しました。
拙宅で使っている電子レンジの付録のレシピ本にも確か同じような作り方の「牛丼」がありました。