りんきの独楽 あらすじ
ある商家の旦那は寄席を聞きに行く言ってと出掛けた。
おかみさんはヤキモチ焼きで、旦那が寄席には行かず、女の所に行くであろうと、小僧の定吉を尾行に付けた。途中で旦那に見付かり、帰れと言っていたが気が付くと、もう女の家に着いてしまっていた。
やむを得ず定吉をお妾さんに合わせ、手持ちが無かったのでお妾さんに小遣いを作らせ渡した。
これで買収成功。 おまんじゅうをもらって、そこに有った独楽(こま)を見つけて所望すると「これは辻占の独楽と言って、旦那の独楽を回し、私の独楽と奥様の独楽を回すと、どちらかにぶつかる ぶつかった方にお泊まりになる。 よかったら奥にも有るのでお持ちなさい 。」 定吉はお土産をもらって喜んで、引き揚げてきた。
戸を叩いても誰も出てきてくれない。「だんなのお帰り」と大声で叫んで騙し、開けてもらったが、奥でおかみさんがお待ちだという。
怖い顔をして待っていた。
店を出たが、旦那の足が速くて見失ってしまった。と言いつくろったが、もらった小遣いを落としおかみさんに見付かってしまった。「お前がウソを付くだろうと思って、その後からお清を付けさせたのを知らなかっただろう」。驚いた定吉。全てを白状したら「クヤシイね。そうだったのかい」、「!?」 「お清はウソだよ。」 「あら、全部しゃべってしまった。」
「ところで、旦那はお泊まりなるのかい、それともお帰りになるのかい」「それでしたら、良い物があるんです。この独楽なんです。辻占の独楽と言って昔、花柳界で流行ったんです。この黒い独楽は旦那の独楽、赤いのがお妾さん、地味な色の独楽がおかみさんのです。三つ回して旦那の独楽がお妾さんの独楽に着くとお泊まりで、おかみさんの独楽に着くとお帰りになるんです」。
「わかった、回してご覧。」 「 おかみさんの望み通りにならなくても知りませんよ。三つ回しましたよ。おかみさんの独楽が旦那に近づいた、旦那が逃げる、おかみさんが追いかける、旦那が逃げる。コッツン、今晩はお泊まりです。」 「クヤシイね。もういっぺん廻してごらん。」 「 はい、分かりましたよ。旦那さんおかみさんが怒っていますから今度はお願いしますよ。おかみさんの独楽は旦那の独楽のソバに置きますよ。おかみさんが寄っていった、旦那が逃げる、おかみさんが追う、旦那が逃げる逃げる・・・・・・コッツン、お泊まりです。」 「まあクヤシイ。定吉、いっぺん独楽を調べてごらん。」 「あッ!イケマセンよ。肝心の心棒が狂っています。」
角川文庫「古典落語」にある三代目・柳家小さん師演を読んだのが最初でその後に、二代目・桂文朝師演、現・春風亭小朝師演を聴きました。
噺自体は面白いと思ったのですが、どうもあのサゲがしっくりきませんでしたね。
「心棒が狂いました。」
「当たり前じゃないか?『心棒』が狂えば『独楽』はまともに廻らないに決まっている。どうしてサゲとして成り立つのだろう?」と私の中では「考え落ち」と化してました。
だいぶ後になって、東大落研編「増補落語事典」青蛙房を読んだら「『心棒』と旦那の『心』をかけたサゲ。」としてありました。その時は「ああなるほど。」とは思いましたが。
その後にウィキペディアで「りんきの独楽」のあらすじを見てみたら「旦那の『心棒/辛抱』が狂ってます。」としてあるのです。 この場合、「辛抱」とは何を「辛抱」するのでしょう? 「妾宅」に泊まるのを「辛抱」して「本宅」に帰るということなのでしょうか?
「心棒/心」、「心棒/辛抱」 演じている落語家さん達はどっちの意味にとっているのかしら?とまで思いましたね。
でも理屈な話は抜きにして、旦那、本妻、妾の三角関係のもつれを「独楽」に見立てているのは何とも滑稽ではありますね。 そういう意味では「心棒/心」の解釈が正しいですかね。
こんな展開も考えてみました。
旦那の独楽がお妾さんの方ばかりにくっつくので、 本妻「旦那の独楽調べてごらん。」 定吉「調べてたところでですね。(独楽を持ち上げて調べる仕草)」 すると 旦那の独楽が 「だから今夜は(妾宅)に泊まるってんだよ。」
「怪談 りんきの独楽」・・・・・ってほど怖くもないか・・・・・・。

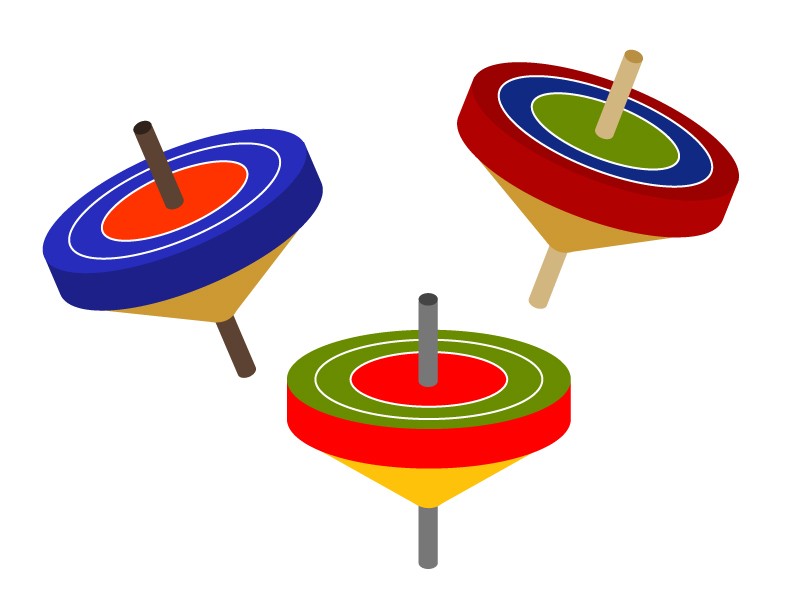


コメント
お古い速記を読むと「心棒」「辛棒」「真棒」など複数に分かれます。これは演者というよりは速記者あるいは筆者による解釈の違いでしょう。
万延二年(1861年)上方の桂松光(しょこう 一説では笑福亭とも)のネタ帳「風流昔噺」には「しんぎ(蛇足注:心木 心棒のこと)くるい落」とありますので、上方は一貫してこの流れから「心」でサゲていると思われます。
ただし、フリガナで「心棒(しん)が狂ぅてます」というのもあります。
速記で読むと伝わりやすいのですが、映像や音源で聴きますと、聴き手によって分かれるのかなぁ~、と感じます。
それを避けるためか、四代志ん生は前半の「喜撰(蛇足注:きせん)」でサゲてました。
立花家蛇足さん、コメントありがとうございます。
>「心棒」「辛棒」「真棒」
なるほど、聴き手や速記者の解釈によって違ってくるケ―スもあるのですね。
「心棒/辛抱」という解釈も聴き手によるものなわけですね。
「心棒」を「シン」と言っている落語家さんもいたのですか。
私は二代目・桂文朝師演をナマで一回、テレビで二回聴きましたが三回目の時に「肝心の心棒が曲がってます。」という言いまわしでサゲてました。
気持ちが「妾」の方へ曲がっている「旦那」の「心」を「独楽」の「心棒」に見立ていればこその言いまわしでしょうね。
「心棒(シン)」という読み方にしても「旦那」の「心」を「心棒」に見立ているのですね。
> 喜撰
「喜撰小僧」は八代目・春風亭柳枝師以降は演り手はいないのでしょうかね。
「喜撰」という茶の銘柄も現代の客にもピンと来ないでしょうね。
清元の「喜撰」は五代目・古今亭志ん生師等多くの落語家によって「稽古屋」の中で歌われてますね。
歌舞伎舞踊としても「六歌仙容彩(ろっかせんすがたのいろどり)」の中で最も多く上演される人気演目です。
小野小町に恋心を抱く喜撰法師が容姿のよく似た茶汲み女お梶を追い回す舞踊で時期も桜満開の季節で楽しくユ―モアたっぷりの舞台です。
明治・大正時代もポピュラーな曲だったのでしょうね。
>ヌーベルハンバーグさん
『喜撰小僧』はあたくしのデータベースによりますと、2006年9月の落語研究会で柳亭市馬が掛けております。
当代ではこの噺に一番ふさわしい噺家だと思います。
立花家蛇足さん。ありがとうございます。
現・柳亭市馬師が演じてましたか。
サゲでウケようというより、自分の美声を生かして、演り手がなくなるかも知れない噺を残していきたいという思いが強いかも知れませんね。