「銭湯で上野の花の噂かな」
皆さんは「桜」といいますとどこが一番印象深いですか?私は数十年前に箱根登山電車の中から見た桜、仕事の関係で済んでいたことのある山口県岩国市内を流れる錦川沿い特に錦帯橋周辺に咲き乱れていた桜の眺めが忘れられません。「あの時どうして手元にカメラがなかったのだろう?」という想いが未だにあるのですが。


現在の私の周辺でも3月28日に桜の開花が見受けられました。

28日に咲いた後29日が雨天だったのでそれで散ってしまうのではと心配したのですが、どうしてどうして桜は思っているよりタフな花でした。

昔から日本人は「花見」イコ―ル「桜」とほぼ定着しているようです。
しかし、「花見」とは名ばかり、「長屋の花見」「花見の仇討」のマクラで振られるように
「お前、花見に行ったんだって、どうだったい。」 「そりやあすごい人手だよ、芋を洗う様だ、酔っ払いは出るしねぇ、喧嘩はあるし、俺はもう懲りちゃったね。」 「そうかい、で、花はどうだったい。」「花?はな、はなあ、あったかな?」
というのが実際でしょうね。
「花より団子」 「桜」よりも「ビ―ル」「おにぎり」「サンドイッチ」「唐揚げ」・・・・・ってとこですかね。

私が申し上げるまでもなく「長屋の花見」も「花見の仇討」もまず「花」を愛でる内容の話ではありませんね。
「長屋の花見」 あらすじ
ある日貧乏長屋の住人達に大家さんから呼び出しがかかる。
誰もまともに家賃なんて払ってないからきっとその催促だ
場合によっちゃあいよいよ追い出されるのかと長屋の住人達は戦々恐々としながら大家さんのところへ
すると意外なことに大家さんからの呼び出しの理由はこのようなことだった
大家「うちの長屋は世間様からヤレ貧乏長屋、貧乏長屋と呼ばれて景気が悪くて仕方がない。今日はみんなで花見に行って陽気に騒いで一つ貧乏神を追い出そうじゃないか。酒や肴はこちらで用意したから安心しておくれ。この通り、一升瓶にこの重箱にはカマボコと卵焼きが入っている。なあに心配するなみんな私のおごりだ。」
大家さんの意外な提案に長屋の住人は大喜び、さっそく上野の山へ向かおうと盛り上がっているところで大家さんの種明かし。
一升瓶の中身はお酒ではなく番茶を煮出して薄めたもの カマボコは大根のコウコと卵焼きの正体は黄色いタクワン。 住人「さすがは貧乏長屋の大家さんだ これじゃあガブガブのボリボリだよ」 大家「まあいいじゃないか。こっちが気分良く盛り上がれば周りから見たら酒盛りしてるように見えるさ」
妙なパフォーマンスに付き合わされることになった住人達は妙な心持ちを抱えながら上野の山へ。 楽しそうに振舞うのに四苦八苦。
住人「じゃあお茶…じゃなくて酒をついでくれ おっとっと!おうそんなについで俺に恨みでもあんのか」

大家「さあさあ熊さん卵焼きを食べとくれ。」
熊「すいません最近歯が悪いもんで。」
大家「卵焼きを食べるのに歯なんて関係ないだろう。」
大家「八っつぁんもカマボコをおあがんなさい。」 八「へえ 私はこれをしょっちゅう食べてまして。細かく刻んで刺身の添え物にもしますし、腹の具合が悪いときなんかカマボコおろしにいたしやす」 大家「カマボコおろすやつがあるか。」
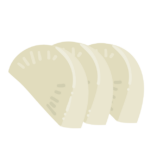
中身が偽物だけになんだかチグハグ。 そこへ住人の一人が 住人「大家さん、近々この長屋にいいことありますよ。」 大家「どうしてだい?」 住人「茶碗の中で酒柱が立ってます。」
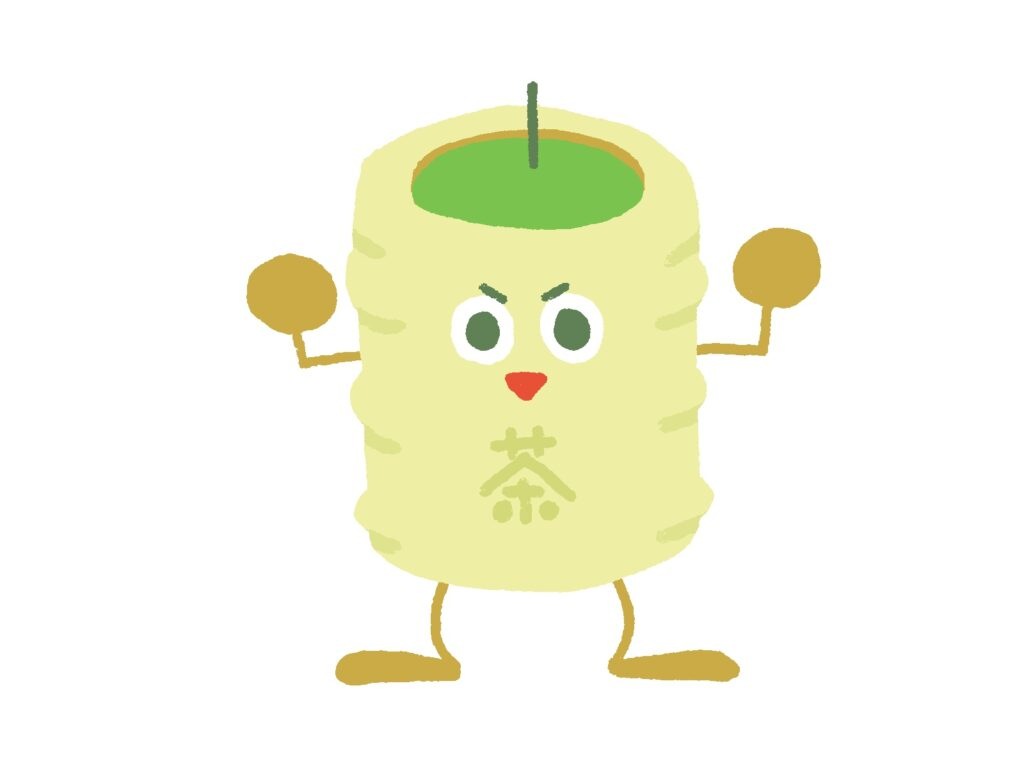
関西の「貧乏花見」を、明治の末に、三代目・蝶花楼馬楽師が改作したもので、当時の題名は「隅田の花見」と言ったそうです。
その後、四代目・柳家小さん師が更に手を加え、今日の「長屋の花見」になったそうですね。
以前に深川書房「落語界」で八代目・都家歌六師により「噺家声の博物館」というコ−ナ−があり、その中で三代目・馬楽師の「隅田の花見」のSPレコードを紹介していたのですが、サゲは 住人が「酒」のフリで「茶」を飲み、酔ったフリをしながら「いい心持ちだ」大家「『いい心持ち』ってどんな『心持ち』だい?」住人「ちょうど去年の夏、井戸に落ちたような『心持ち』です。」としてました。「酒柱が立ちました。」は四代目・小さん師の考案でしょうか。
サゲ方は落語家さんによってまちまちですね。 私が最初に聴いた二代目・桂文朝師は「この酒は100グラムいくらですか? 」「100グラムいくら?てえ奴があるか。」 でおりてました 。 十代目・金原亭馬生師は、「茶」を「酒」のフリで飲んでいた住人が「酒乱」のフリして暴れ出す。 大家「どうしたら、酔いが醒めるんだ?」住人「本物の『酒』を飲ませてくれ。」 現・瀧川鯉昇師は長屋の花見の宴によその花見客がなだれ込んできて大盛り上がり。 大家「大勢の人が集まってきたねえ。これ、みんな本物だねえ。」住人「いえ、これも、あらかたサクラでございます。」 中には、元の「貧乏花見」のように長屋の住人たちが喧嘩をし出した。それを良い事に、長屋の連中は酒肴を失敬して、本格的な花見の酒宴となった。逃げ出したグルプの中の幇間が、ここぞとばかり文句を付けにやってきたが、反対に長屋の連中に脅かされた。「この野郎、何しに来やがった」、「へぇ、お銚子のお替わりを持って参りました。」
私的にはこの長屋の人たちに幸運をつかんで欲しいという願いから、「酒柱が立ちました。」とサゲたいですね。
「長屋の花見」の登場人物たちは景気づけのために「花見」に行くわけですね。 「偽物」とは言え「飲み物」「食べ物」を供にしているわけですね。
私も「花見」の場所で酒を飲んだり弁当を食べたりするのは好きですけど、最近ではスマホやデジカメを持って「桜」などの花を撮影するのも好きなんですよね。 写真や動画を撮ってブログに載せたりYou tubeに投稿したりとかね。 「花」より「団子」、「団子」より「写真」ですね。
この数日、雨空だったのですが今日は久々に晴れました。 「桜」に限らず「花」はこういう日に撮影したいものです。




コメント
桜と言えば……、ワシントンでしょう!
「桜の枝を折ったのは私です」という嘘エピソードのジョージ・ワシントンではなく、全米桜祭りのワシントンDCです。
それはさておき、今は王子なのでやはり飛鳥山ですね。
でも、「花より団子」ならぬ「花の下より鼻の下」かなぁ~。これは下ネタではなく鼻の下、すなわち糊糊口を凌ぐことです。下ネタなら「花の下よりへその下」ですね。
「酒柱」はヌーベルさんが紹介された三代馬楽のレコードの元になった速記「隅田の花見」(馬楽新落語集 明治39年 小槌会刊)に出て来ます。恐らく馬楽が嚆矢だと思います。
馬楽を敬愛した四代小さんも「馬楽(三代)を聴いて覚えた」と安藤鶴夫に語っております。月刊東宝四号「落語と豫備知識」より(東宝出版社 1946年 昭和21年)
立花家蛇足さん
いつもコメントありがとうございます。
三代目・蝶花楼馬楽師も「酒柱」を取り入れてましたか。
やはりSPレコードにはそこまで入れられなかったのかな。
三代目・馬楽師の「隅田の花見」の速記を一度読んでみたいですね。
講談社Super文庫の落語名人大全に、「居残り佐平次」の速記は載っているのですがね。
無料の会員登録が必要ですが、国立国会図書館デジタルコレクションで閲覧可能です。
一応、説明ページのリンクを張っておきます。マイナカードや免許証で登録可能です。
https://www.ndl.go.jp/jp/use/digital_transmission/individuals_index.html
「口演速記明治大正落語集成 全7巻」が先般公開されましたので閲覧できます。
当該ページをリンクします。(上記、会員登録が必要です)
https://dl.ndl.go.jp/pid/12467114/1/152
その他にも、角川版の圓朝全集を初め絶版本や入手しづらい稀覯本など落語関係の史料も膨大な量が公開されてます。
検索の仕方を覚えると探し物が捗ります。
立花家蛇足さん。情報ありがとうございます。昔の名人の速記とかなかなか見れるもんじゃないとばかり思っていましたが、是非参考にさせて頂きます。