暇をもてあました長屋の若者が数名集まり、それぞれ嫌いなもの、怖いものを言いあっている。「幽霊」「クモ」「ヘビ」「コウモリ」「毛虫」「アリ」と言い合う中にひとり、「いい若い者がくだらないものを怖がるとは情けない。世の中に怖いものなどあるものか」とうそぶく男がいる。他の男が「本当に怖いものはないのか」と聞くと、うそぶいていた男はしぶしぶ「本当はある」と白状する。「では、何が嫌いなのか」と念を押され、男は小声で「まんじゅう」とつぶやく。男はその後、「まんじゅうの話をしているだけで気分が悪くなった」と言い出し、隣の部屋で(あるいは、自分の長屋へ帰って)寝てしまう。
残った男たちは「あいつは気に食わないから、まんじゅう攻めにして脅してやろう」と、金を出し合い、まんじゅうをたくさん買いこんでお盆に山盛りし、男の寝ている部屋へ運び込む。目覚めた男はまんじゅうを見て声を上げ、ひどく狼狽してみせながらも、「こんな怖いものは食べてしまって、なくしてしまおう」「うますぎて、怖い」などと言ってまんじゅうを全部食べてしまう。一部始終をのぞいて見ていた男たちは、男にだまされていたことに気付く。怒った男たちが男をなじり、「お前が本当に怖いものは何だ!」と聞くと、「このへんで、熱いお茶が1杯怖い」

NHK−Eテレのキッズ番組「にほんごであそぼ」では私が知っている限り、現・立川志の輔師、小錦八十吉師のが主役となり二回程、寸劇化されてます。 そのくらいわかりやすくポピュラーな噺なのですね。
関東の寄席では大抵10〜15分間で演じられるようです。
ところが今から数十年前に「音源」というものが「CD」ではなく「レコード」で市販されていた時代に、「饅頭怖い」に関して「えっ!?」と思うような体験をしたことがあります。
キングレコード「落語特選」のカタログを見ていたら、演者は六代目・笑福亭松鶴師なのですが「饅頭怖い」がLPのA、B両面にわたって収録されている盤があるのです。 つまり、六代目・松鶴師は「饅頭怖い」一時間前後かけて演じているのですね。 「そんなに長い噺だったかなあ?」とその時は思いました。

その後、ラジオやテレビで二代目・桂枝雀師演、現・桂文珍師演を聴いて「なるほど時間がかかるわけだ。」と納得しましたね。「饅頭」の本題に入る前の各々の「好きなもの」「怖いもの」の話題の件が関東の演出の数倍の時間をかけているのですね。
●「好きなもの」の噺をしていると「食べ物」でなく「朧月夜」が好きだという男がいる。 「朧月夜の晩に一人でわしがブラ~ブラ歩いてると足に触ったもんがある。ヒョッと見たら、これが風呂敷包みや。開けて見たら金が入ってんねや。で、うち持って帰ってよぉ勘定してみるっちゅうとやなぁ、札やら銀貨やら取り混ぜになってやで、勘定が二十三万四千五百六十七円八十九銭。これをこぉ警察へ届けとくわ。こっちの忘れてる時分に警察から呼び出しや、何やろなぁと思て行てみたら、この風呂敷包みの一件。「お前はこんだけの大金を拾いながら自分の懐へも入れずによぉ正直に届け出た。偉いやっちゃ、見上げたもんや、天晴れなやっちゃ」せんど誉めてもろぉて、この二十三万四千五百六十七円八十九銭もらうのんが好きや。」
●怖いものの話をしていると「狐」が怖いという。「罠にかかった狐が命乞いをしている。助けてくれるなら、一度狐がどんな風に人を化かすお見せするという約束。その約束を信じて見ていると狐が美女の化けて若い男を誘惑し小屋の中へ二人で入っていく。壁の節穴から覗いているうち暗くて見えなくなり、何やら臭い。頭の上に何かばさっとかかってくる。そのうち誰かに『何をしてんねん危ない!』と声をかけられよく見たら馬の尻の穴を覗いていた。」

●夜道を歩いていると、橋から川へ身投げしようとしている女がいる。止めるがどうしても死ぬと言って聞かない。勝手にせいと放置していくやがて川に飛び込む音。気にせずに歩いていくと後から身投げした女が全身ずぶぬれ姿で後から追ってきて・・・・・・・・・・。
といった話をそれぞれ五分ぐらいかけて話す件があるのですね。 「饅頭」の話になるまで20~30分間近くあるのです。 それから「饅頭」の話に入り、サゲまでいったらかなりの時間ですね。 ネットで配信されている、六代目・笑福亭松鶴師演を聴くと45分間ありましたね。 なるほどLPレコードならA、B両面かかりますよね。 関東では「留さん」こと九代目・桂文治師は関西の演出の流れで「饅頭」の前までの件を「好きと怖い」という題で演じていたようですね。
また「饅頭」の件では饅頭怖いと震えだした男を関東ではその家の隣の部屋に寝かせるのに対し、関西ではその男の家まで送っていって寝かせています。
関西の演出は関東に比べるとかなりきめ細かいものがあるケースが多いですね。「かぼちゃ屋」の元の「みかん屋」を聴いてみると、「上を見る」という商売方法もかなり細かい駆け引きがありますし、「二番煎じ」もかなり細かい段取りがあります。
聴き手に合わせるためなのでしょうか、細かい段取りを簡単にしているのも関東の演出の良いところかも知れませんね。
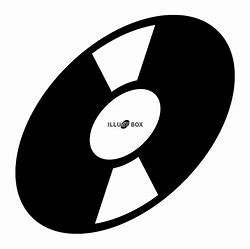


コメント
『饅頭怖い』、面白い経歴の噺ですよね。
明の李卓吾の笑話を元にした古~い小咄で、寛政年間に東南西北平が実演向きの江戸小咄にしました。
それが上方に渡り一席物に仕上げられたようです。
それを江戸に移植したのが初代蝶花楼馬楽と言われております。
あたくしは高座で接したことはありませんが、過去には落語研究会・東京落語会・東横落語会などでも掛けられてます。
1973年9月の落語研究会では六代笑福亭松鶴が42分の高座を演じました。
立花家蛇足さん
饅頭の由来の話勉強になります。ありがとうございました。
三国志の時代から始まっているのですね。
最近、近所のス―パ―でマンドゥなる食品を売っているんです。冷凍食品も出ているんですけど。見た感じ食べた感じは大型の餃子を思わせるんですけど、言葉の響きは「饅頭」を思わせるのですね。十年前にトルコへ旅行した時にカイセリのホテルで食べた「マントゥ」とも同類かなと思ってるんですがね。
立花家蛇足さん。コメントありがとうございます。明→江戸→上方→江戸 確かに変わった経歴ですね。明時代の中国の饅頭はやはり肉饅頭ですかね。
>ヌ―ベルハンパ―グさん、
原文では「有窮書生、欲食饅頭」と書き出してあり、また途中「吾畏饅頭」とありますので、いずれも饅頭のみの記述です。
サゲも「更畏臘茶両椀爾」(蛇足注:「臘茶」茶葉を蝋で固めた高級茶)と良いお茶を両椀ですから二杯所望してますね
何を包んだのか? あるいはただの蒸しパンなのか? 原文からでは分かりません。
ただし饅頭の原典は諸葛亮孔明が「蛮頭」という晒し首を嫌い小麦で見立てた「饅頭」を代わりにした、という故事からですので、何も入っていない蒸しパンだったのかもしれませんね