「考え落ち」とは考えないとその意味やおかしみがわからない「落ち」を指しますね。
良く上演されるのが「そば清」「芋俵」「千両みかん」「疝気の虫」などですね。
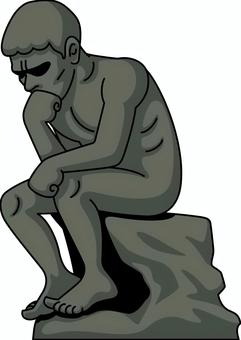
「そば清」
「盛りそば」の大食いの賭けで負けたことがないことで有名な清兵衛さん通称「そば清」。
三十枚は平然と平らげるが、ある日のこと五十枚食べたら一両もらえるという賭けを持ちかけられる。
これはやり遂げる自信がない。
そんなある時商用で信州に出かけたところ、その山奥で大きなウワバミが狩人を丸呑みしているところを目撃する。
人間の大人を一人丸呑みにしたウワバミの腹は大きく膨れあがり、ウワバミも苦しそうにしていたが、近くに生えていた黄色の草(演者によっては赤い草)を舐めると膨らんでいた腹はたちまち萎んでいく。
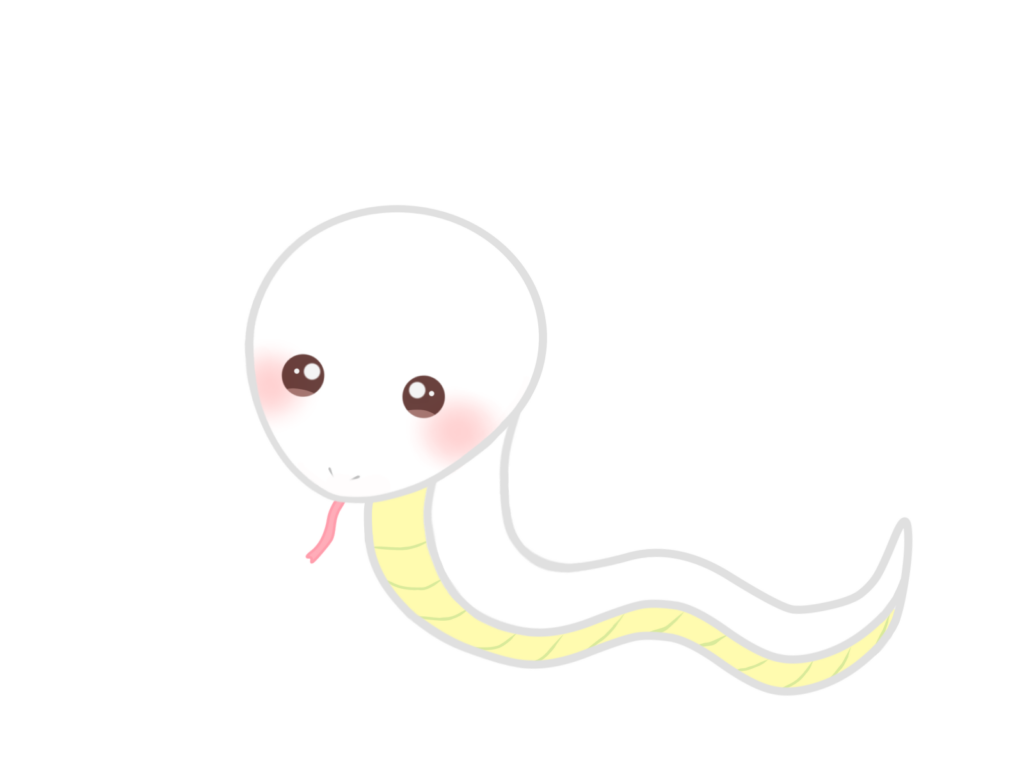
「あの草は食べた物を速くこなれさせる薬に違いない。これさえあればあの賭けに勝てる。」と数本摘んで江戸に戻り、「盛りそば」五十枚で一両の賭けに挑む。
賭けを持ちかけた人たちが見守る中、清兵衛さんはたちまち四十数枚の「盛りそば」を平らげて、あとわずかな枚数で五十枚というところで、 「ちょっと一服。」と隣の部屋に入り襖を閉めて例の草を舐め始める。
清兵衛さんがなかなか出て来ないので気になって襖を開けると、そこには清兵衛さんはいなくて「そば」が羽織を着て座っていた。
私は最初に偕成社 「少年少女名作落語」に「そばの羽織」という題で載っいたのを読んだのですがはっきり言ってわからなかったですね。
挿絵にあった人型に固まった「そば」が羽織を着て座っている姿の不気味さが忘れられないのですがね。
後の解説に「ウワバミが舐めたのは人間を溶かす草だった。」と記してあったおかげで理解出来た有様でして。
後になって知ったのですが、このオチは最初は理解されずになかなか笑いが取れずにいたのですが、初代・柳家権太楼師がオチの説明を入れたところ初めて笑いが来て、それから多くの落語家がその説明を入れるようになったそうですね。
私が聴いている範囲では五代目・古今亭志ん生師、三代目・三遊亭小圓朝師、三代目・古今亭志ん朝師、六代目・三遊亭圓窓師、六代目・三遊亭円楽師は説明付きで演じてました。
十代目・金原亭馬生師は説明がありの時と無しの時がありましたね。十代目・馬生師はオチよりも清兵衛さんと賭けを持ちかける人たちの対比の面白さで笑いを取ってましたが。
主題が「そば」だけに説明の無い方が江戸前で粋な感じがするという意見もあるようですが、現代の観客の中には説明無しで理解出来る人はどのくらいいるのでしょうか
現・柳家さん喬師はオチの説明はしないのですが噺の途中でオチを理解するためのヒントを振る演り方をしてました。
どういう演り方が望ましいかなかなか答えは出ないでしょうね。
そもそも「落語」という物自体が多くの落語家さんたちによって「ああでない。」「こうでない。」と何べんも練り直されながら後世に残っていくものでしょうからね。
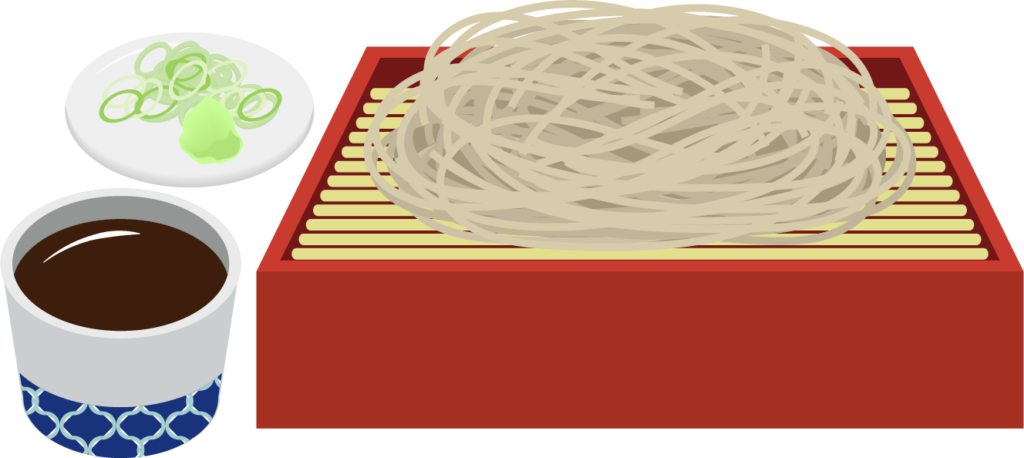
かなり「そば清」で話がながくなってしまいました。
次回もっと他の噺の「考え落ち」について考えてみたいと思います。
今回はこの辺で。
「
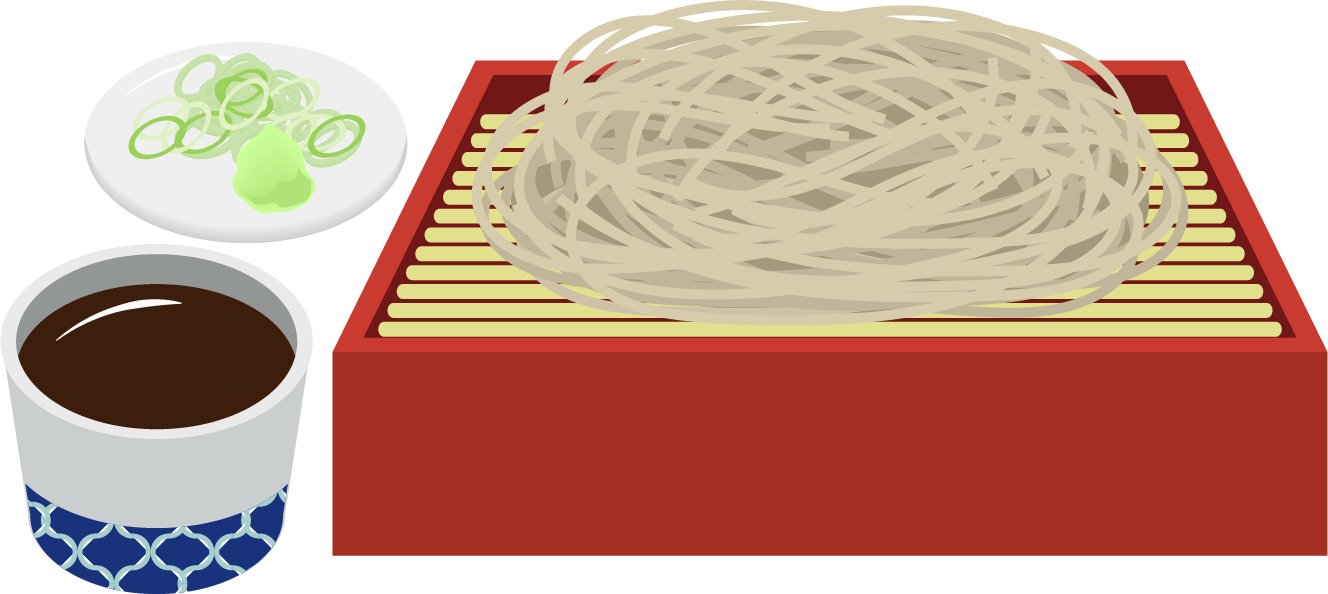

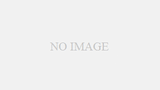
コメント