今回は現在はほとんど演じられない落語の「考え落ち」について考えてみたいと思います。
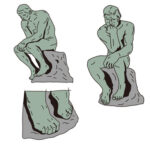
「蛸坊主」
八代目・林家正蔵師(林家彦六)、五代目・春風亭柳朝師の後は演る落語家はいないようです。
不忍池の池端の料理屋
高野一山の坊主4人、実は偽坊主が料理屋にやってきて飲み食いしている。
最初に、生臭ものはならぬぞと断っておいて、しかし亭主がかつお出汁を取っていたことに因縁をつける。
修行の成果が無駄になったので、この家で養ってもらおうというのだ。
寺社奉行の管轄である上野の山で強請をしても、町奉行所はやってきてくれない。

たまたま居合わせた老僧が仲裁に入ってくれる。
老僧は、けっして急がず、タメを十分とってゆっくりゆっくり喋る。
「鯛の刺身を食ろうても、愚僧は豆腐と思う」と。そうすれば修行の妨げにはならない。
そして、なぜ生臭いものをまったく口にしたことがないのに鰹がわかったのかと問う。
どこまでもゆっくりした口調で、ついに偽坊主どもを一喝する。われの面体を知らずして、よくも高野山で修行できたと言えるなと。この生臭坊主、蛸坊主。
正体がバレ、ついに腕づくで老僧に襲い掛かる偽坊主ども。しかし老僧は、見かけに似合わず怪力無双。
池に逆さに放り込まれ、4人ひっくり返って8本足。まさに蛸坊主。
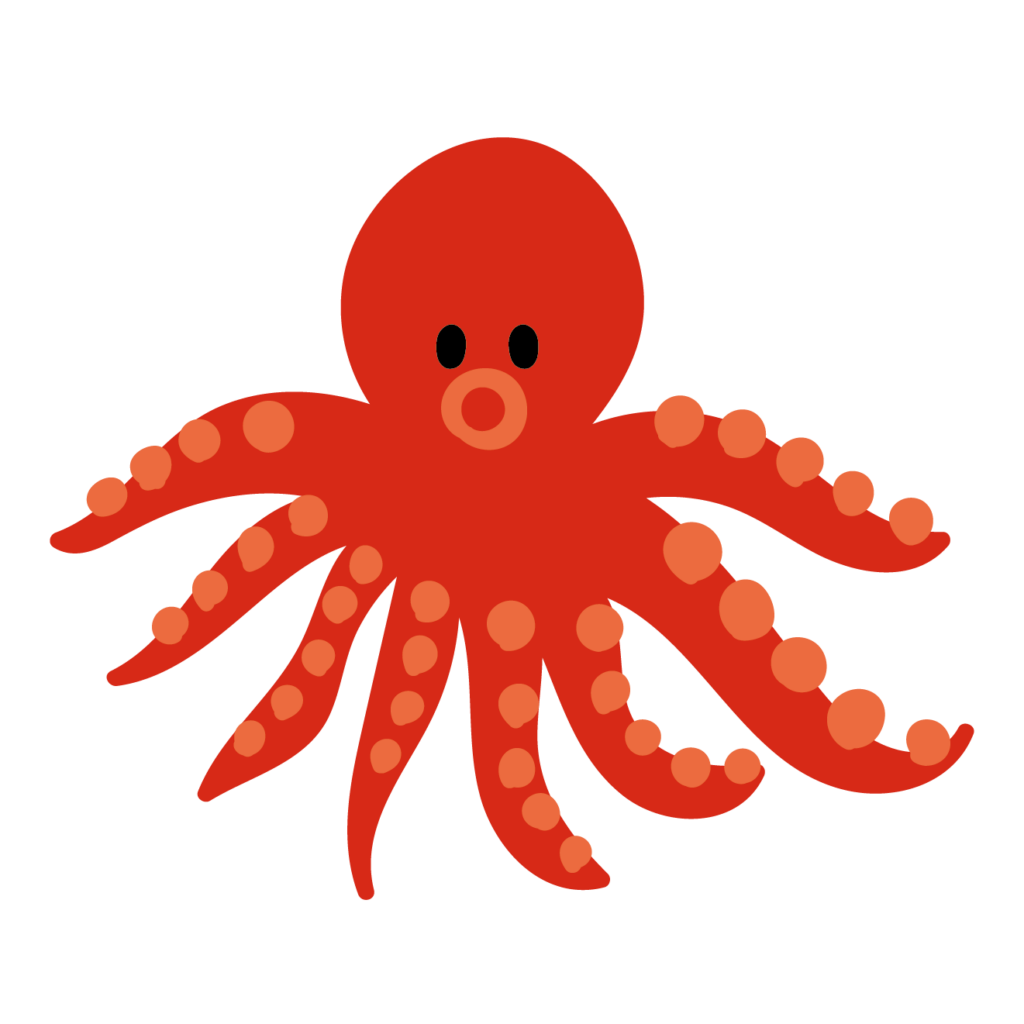
オチも良くできているし、性質の悪い強請り集りを成敗するという。
イマドキのユーチューバーにもこういう人っているんじゃないですかね。
そういう意味でも是非誰かに演じてほしい噺の一つですね。
「考え落ち」で傑作だなと思う噺で現代は恐らく全く演じられてない噺で「鏡代」があります。
「鏡代」
ある男が呉服屋の娘を見初めて恋煩い。
友達の知恵で、呉服屋の娘に惚れた男が、下女を通じ仕立て物を頼む中に恋文をはさんで送った。
幾日か後、その仕立てが出来たので、期待に胸ふくらませて包みをあけると、中に手紙らしいものが入っている。「さては色よい返事か」と喜んで開けてみると、1円札が包んであって、表書きに「お鏡代」と書いてあった。

「私に『恋文』をよこす前にこのお金で『鏡』を買って自分の顔をよくごらんなさい。」という意味なんですけど遠回しに「鏡代」と書いた金包みをよこすところに大家のお嬢様らしい慎ましさもありこの噺の可笑しみもありですね。
昔は二代目・柳家つばめ師がよく高座にかけていたそうです。
近年では六代目・三遊亭圓窓師が一度復活させたようですがその後は演じられたという噺は聞きませんね。
先述の通りかなりよくできたオチだと思いますので是非また復活させてほしい噺です。
以上、4回に渡って「考え落ち」に関しての私の「考え」を記させていただきました。
「芝浜」「あくび指南」「寿限無」「まんじゅう恐い」の落ちを「考え落ち」であるとあるネットに記されてましたが私としては違うんじゃないかなと思うのですが。
また機会を設けて落語のオチについて考えてみたいと思います。

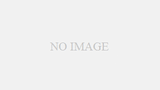
コメント