今回は「艶笑噺」の「考え落ち」について考えてみましょう。

「艶笑噺」の「考え落ち」で思い浮かぶのが「疝気の虫」。
「疝気の虫」あらすじ
ある医者が夢の中で変な虫がいるので潰そうとすると虫は命乞いをして「自分は疝気の虫といい、人の腹の中で暴れ、筋を引っ張って苦しめるのを職業にしている。蕎麦が大好物で食べると威勢よくなって大暴れし、嫌いなものは唐辛子で、それに触れると体が腐って死んでしまうので、唐辛子を見ると別荘、男の金の袋に逃げ込むいう。
夢から醒めた医者は、治療に役立つかも知れないと、疝気で苦しんでいる男の家に往診に出かける。おかみさんに蕎麦と唐辛子を用意させ、蕎麦をおかみさんに食べてもらい、その匂いを亭主にかがせる。

亭主の腹の中にいた疝気の虫は大好物の蕎麦の匂いがするので、上がって来て亭主の口から、おかみさんの口に飛び移り、腹の中で大暴れするので、今度はおかみさんの方が苦しみ出して七転八倒だ。疝気の虫が出て行った男はそばでケロリとしている。

医者はこの時とばかり、用意してある唐辛子をおかみさんに飲ませるさせる。上からの天敵の襲来に仰天した疝気の虫は急いでいつもの避難場所に逃げ込もうと、一目散に腹を下るが、
「別荘はどこだ、別荘は・・・・?」
「志ん生艶ばなし」(立風書房)掲載の五代目・古今亭志ん生師演では此の後に「いくら探しても別荘が見つからなかったという。」としてありましたが、元気な頃の師は「別荘だっ!!」と周りをキョロキョロする仕草を見せてお辞儀して下りていたそうですね。
三代目・古今亭志ん朝師演の音源を聴くと「別荘ッ!別荘―ッ!!」の後に「ふあああッ!!」と恐らくは「トウガラシの水」にやられた「疝気の虫」の「断末魔(?)」と思われる悲鳴がついてます。
七代目・立川談志師演の動画では「別荘!別荘!」で辺りをキョロキョロ見廻した後で、地に戻って「客人よ。これ以上何を語れと言うのか?」と下りてます。
現・柳家権太楼師は「トウガラシの水」で体外に追い出された「疝気の虫」を捕まえて、 医者「疝気の虫め!」 虫「助けて下さい。」
と演ってます。師の考え方でしょうが私は元の「別荘」をキョロキョロ探すオチの方が面白いと思うのですが。
私の考えでは「艶笑噺」は「考え落ち」にした方が、想像力をかき立てられて面白いと思いますね。
江戸小噺でこんな話がありましたね、
猫が台所にあった赤貝に手を出して前足をはさまれる。誰かに取ってもらおうと二階に上がると、「誰だい、下駄はいて二階へ上がって来るのは」
飼い主の女が助けて、湯上りの浴衣で猫を抱こうとするが、あやまって落してしまう。猫はひらりと着地して、上を見上げると、何を見たのか「フーウッ」
現代でも「赤貝」「あわび」みたいな言い回しはかなりありますからね。
「考え落ち」ではなくて「見立て落ち」という意見も多いかも知れませんね。
現代の艶笑噺では現・鈴々舎馬風師が演っていた小噺でこんなのがありました。 子供「お母さん。何で僕には弟も妹もいないの?」母「おまえが早く寝ないからですよ。」
これは聞き手に「考えさせること」自体がオチかも知れませんね。
我々も日常の中で「考え落ち」のついた「艶笑噺」をする事はあるのではないでしょうか。
以前、「志村けんの大丈夫だぁ」で、すわ親治氏が良く「うちの子が可愛いいんですよ。隣の旦那そっくりで。」「隣の子が可愛いんですよ。私にそっくりで。」なんて
「都市伝説」の本にも「艶笑」「考え落ち」に近い恐ろしい結末の話があるのですが記していたらキリがないので今回は控えます。
次回は現在はほとんど演じられなくなった落語の「考え落ち」に考えてみたいと思います。

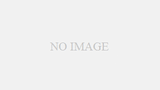

コメント