以下は落語「厩火事」のあらすじ。
髪結いで生計を立てているお崎の亭主は文字通り「髪結いの亭主」、昼間から遊び呆けて酒ばかり呑んでいる怠け者だった。そんな年下の亭主と口喧嘩が絶えないお崎だが、しんから愛想が尽き果てたわけではなく、亭主の心持ちが分からないと仲人のところに相談を持ちかける。
話を聞いた仲人は、お崎にふたつの逸話を聞かせる。 ひとつは、唐土の孔子の逸話。 孔子の愛馬が、弟子の不手際で起きた火事で焼け死んでしまった。 だが孔子は愛馬の死を咎めずに弟子たちの身を心配し、それゆえに弟子たちの信奉を得た話。
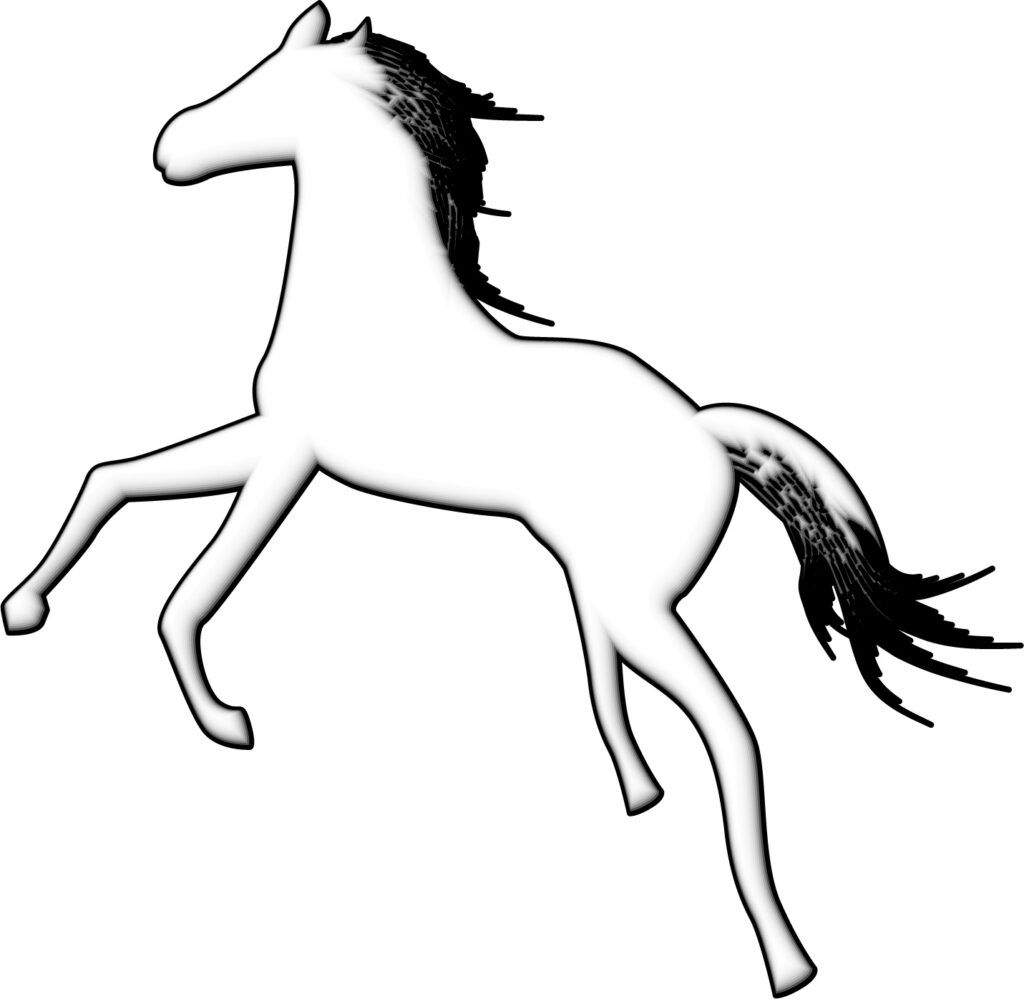
今一つは瀬戸物を大事にするあまり、家庭崩壊に至った武家の話だった。 これら二つの逸話を下敷きにして、お崎の夫が大切にしている瀬戸物をわざと打ち壊す。 それを見た夫がどのように反応するかを見定めて、身の振り方を考えたらどうか、との提案だった。
帰った彼女は早速、夫の目の前で瀬戸物を打ち壊した。 結果、夫は瀬戸物よりも彼女の方を心配した。 感動したお崎が「そんなにあたしのことが大事かい?」と叫ぶ。

対する夫は「当たり前だ、お前が指でも怪我したら明日から遊んで酒が呑めねえ」
1990年フランスで下記のあらすじの映画がパトリス・ルコント監督により製作上映されました。映画の題は「Le Mari de la coiffeuse(髪結いの亭主)」
彼には少年の頃からの憧れがあった。 シャンプーとコロンの香りが漂う理容師の妻を持つこと。 中年になってから彼はその憧れを手に入れる。 シャンプーとコロンの香りが漂い、しかも中年の自分よりもずっと若く美しく、肉感的な身体を持つ妻を・・・・・・。

そして彼と妻の濃密だけど平穏な日々が始まる。 サロンの客の調髪に勤しむ妻の姿を側で見つめていたり、或いはクロスワードパズルに興じたり、客に中東のダンスを踊って見せたり、そして妻とは濃密な時間を過ごして・・・・・・・・。
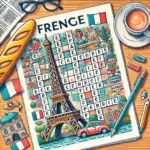
そんな彼に妻は「絶対に愛しているふりだけはしないで・・・・・・。」 惜しみなく妻に愛を注ぐ彼。 夫の愛に包まれ幸せを感じながらも妻の胸中にはある不安が漂う。 この幸せは何時まで続くのか。 現在夫は自分を愛してくれているがいずれ飽きられてしまうのでは。 それに自分は夫よりもずっと年齢が若い。 夫は自分より先に世を去ってしまうだろう。自分は独りぼっちで不幸に・・・・・・。 外は大雨「買い物に行く。」と言って出かけた妻は水嵩の増した川に身を投じて遠いところへ旅立ってしまう。

妻がこの世にいなくなってしまったという現実を受け入れることが出来ずに彼は今日もサロンに来る客に「妻はそのうち帰って来ますから・・・・・。」 或いは客に中東のダンスを踊って見せたり・・・
エラそうにあらすじを記しましたが、実は私は日本公開時にこの映画を観たわけではなく、その十数年後に仲間内で飲みに行ったショットバーの店内のテレビに動画が流れていたのを見て、店のママさんにタイトルを尋ねたところ「髪結いの亭主」と聞かされ「あれ?外国映画のようだけど『厩火事』を連想させるタイトルだな?」と思い興味を持ち始めました。 「Le Mari de la coiffeuse」の単語を一つずつ拾ってGeogle翻訳すると「美容師の夫」となります。 フランス人が日常生活で「ちょん髷」「丸髷」を結っていたなんて話は歴史上にも見当たらない話なので「髪を結う」仕事もあり得ないのですけど。 名前は存じませんが文化的に本来日本だけのものであるはずの「髪結いの亭主」というワ―ドをフランス映画のタイトルに当てはめた翻訳の先生を何とも「粋」だなと私は勝手に思っております。
「厩火事」を聴いた後で「Le Mari de la coiffeuse(髪結いの亭主)」を見て見ると、パトリス・ルコント監督は日本の落語の「厩火事」という噺を何がで聞き知っているのじゃないかなと勝手に思いたくなる件があります。
「厩火事」「髪結いの亭主」で共通しているのは、まず妻の働きで夫婦の生活が成り立っていることであるのはここで申し上げるまでもありません。
違いは「厩火事」の亭主の八公(演者によっては半公、新公)は妻お崎の稼ぎを当てにたまに飯の支度はするものの一日中酒を飲んでいる男なのに対して、「髪結いの亭主」アントワーヌは妻マチルドの働く姿をまぶしく見つめながらも順番待ちのお客の相手をすること、妻との濃密な時を過ごす幼い頃に憧れていた宝石のような日々を大事にしていること。 彼なりにこの上ないリア充しているってことですかね。
妻たちの共通点は、お崎もマチルドも夫とは年の差婚であり、夫の愛に不安を感じていること。
八代目・桂文楽師演「厩火事」のお崎のセリフを借りると 「あの人よりもこっちが歳が若けりゃよござんすよ。七つも歳が上なんじゃありあせんか。(中略)皺だらけの婆さんになっちまってどうにもこうにもしょうがなくなっちまって、病気ンでもなって寝ててごらんなさいな。若い女でも引きずり込んで変なことされた日にゃいい心持ちしないでしょ。そん時食いついてやろうと思っても歯も何にも抜けちまって土手ばかり……‥。」 「あんな優しい亭主は鉦と太鼓で捜してももう生涯に持つことはできないと思うほど親切にしてくれることもあるんですよ。」 「あん畜生早く死んじまえばいいと思うこともあるんですよ。だからあの人が本当に人情があるんだか、不人情なんだか、死に水を取ってくれる人間なんだか、あの人の料簡てえものがふわふわしてて、ちっともわたしにわからないんですもの。」
マチルドは自分より年回りが上の夫の愛情を感じながらも「絶対に愛している振りはしないで……‥。」 夫が自分に与えてくれている愛に何か確かなものを感じられずにいたのでしょうか。最後の彼女の気持ちは、下記の書き置きに綴られてました。あなたが死んだり、 わたしに飽きる前に死ぬわ。優しさだけが残っても それでは満足できない。不幸より死を選ぶの。抱擁のゆくもりや、あなたの香りや眼差し、キスを胸に死にます。あなたがくれた幸せな日々と共に死んでいきます。息が止まるほど長いキスを贈るわ。愛してたの、あなただけを。永遠に忘れないで。
お崎は夫の愛情への不安・悩みを仲人にぶつけました。 しかし、身寄りがいないらしいマチルドはその悩みを相談出来る相手はいなかったようです。そして、夫の愛情を身体で受け止めた大雨の夜、先述の書き置きを残して悲劇の選択をしてしまう。
お崎にしても仲人に相談出来たとはいえ、「お前に怪我でもされてみねえ。明日から遊んでて酒が飲めねえ。」の答えをどう受け止めたかも気になるところですがね。
「原作を読み込んだら二度と本を開かない。」 「大切なのは心に残ったものは何か、ということ。それを理解し、自分のものにしたうえで表現することが大事。」というのがパトリス・ルコント監督の映画製作方法だそうですね。
このやり方は宮崎駿監督、六代目・笑福亭松鶴師に似ているなと私には思えます。 宮崎監督は自分が見たものの記憶からイメージを膨らませ、それをアニメーション上に展開していくという製作方法で、スタッフたちにもそれを求めているそうです。六代目・松鶴師は晩年、「何もかも一からやり直しですわ。」と今まで自分が手掛けてなかった「按摩ごたつ」「二番煎じ」といった噺をネタおろししてましたが、師のネタおろしは速記本などに頼らずに昔先輩たちの高座で聞いた記憶を頼りに噺の構成を練り上げていくやり方だったそうです。
,
ルコント監督は「Le Mari de la coiffeuse(髪結いの亭主)」製作に当たって「厩火事」の噺を何らかの形で聞き知っていたのかななんて勝手に思っています。 機会に恵まれることなどあったらフランス語通訳を通して話を聞いてみたいです。




コメント