明けましておめでとうございます。
昨年12月31日から今年1月1日まで年越しの仕事でした。
初詣には仕事帰りに1月1日の午後に近所の神社に行き、1月2日に
金竜山浅草寺にお詣りしました。

写真の通り、天気は快晴。
雷門の風神雷神像はいつ見ても迫力を感じさせます。
一度、江戸時代の画家・俵屋宗達の「風神雷神図屛風」を実際に鑑賞してみたいと思っているのですがね。
それはさておき浅草寺が舞台になっている落語はどのくらいあるのでしょうか。
私が思いつく限りでは、「付き馬」「粗忽長屋」「あわてもの」ですかね。
「あわてもの」は大部分の落語家は「堀の内」という題で圓山妙法寺を舞台にしているようですが。
小噺では泥棒の噺のマクラによく使われる「仁王門」の噺がありますね。
仲見世から雷門のあたりが舞台になっているのが「付き馬」ですね。
「付き馬」あらすじ
吉原とある妓楼の前で男が何か考え込んでいる。近くの店の妓夫(ぎゆう=男性従業員)が気になって声をかけると男は、叔母が金貸しをしていて、自分は代理としてここの店に掛け取り(=借金の回収)に来たのだが明日まで待ってくれと言われた、家が遠方なので今から帰って明日出直すのはばかばかしい、近くでひと晩を過ごしたいのだがあいにく金を持っていない、と事情を説明した上で、「ひと晩あたしをあんたの店で遊ばせてくれないかな? 明日掛け取りした金で支払いをするから」と持ちかける。帳場が諒承したため男は登楼し、その夜はどんちゃん騒ぎを繰り広げる。
翌朝、妓夫が料金を取りにやって来る。男は妓夫を連れて店を出ると、ことば巧みに妓夫を吉原の外へ連れ出し、銭湯で朝風呂を浴び、飯屋では湯豆腐で酒を飲みながらの朝食を取る。妓夫はそのたびに代金を立て替えさせられる。店を出た後も男はあれこれしゃべりながら男を連れ回す。なかなか金を払ってもらえない妓夫はいらいらを隠せない。
とうとう仲見世通りから雷門まで来てしまったところで妓夫が怒り出すと、男は近所にいるおじさんに金を借りて支払いを済ませようと言って田原町まで妓夫を連れてゆき、ちょっと待っていてくれるよう頼んで一軒の早桶屋(=早桶の注文販売を手がける葬祭業者)に入っていく。
男は店主に向かい、通りの向こうに立っている男の兄貴が死んだので早桶をこしらえてくれと小声で頼み、店主が引き受けると「このおじさんがこしらえてくれるとよ」と妓夫を店に呼び入れた上、「ちょっと用事があるから」と姿を消してしまう。
店主が金を出してくれると思い込んでいる妓夫と、早桶を注文されたと思い込んでいる店主との会話はなかなかかみ合わず、やがて店の職人たちが作った早桶を運んでくる。仰天した妓夫は男にだまされてただで飲み食いされてしまったことに気づく。妓夫の話を聞いた店主は「見抜けねえてめえも間抜けだ」と激怒し、早桶の材料費を置いていけと妓夫に迫る。金はないと妓夫が答えると、店主が職人たちに向かって
「おい、廓内(なか)まで付き馬に行け」
脚注
噺の後半で浅草寺の境内から仲見世通り、雷門のあたりの描写がありますが、今は見られない店もありますね。「紅梅焼き屋」さんが今はありませんね。
「人形焼き屋」さんは今もありますが「卵の殻」が店外に積んである光景はないんじ
ゃないですかね。
鳩豆売りは平成15年に撤去されたとか。
「付き馬」の時代の光景は見られなくなったものはあるもののこの十数年の間に新たな名物が生まれてきているのでは。
写真にある「揚げ饅頭」もその一つでしょう。

この店では他に、他に「イチゴ大福」「モンブランソフトクリーム」なども売ってました。
他に「カレーパン専門店」「メロンパン専門店」など少なくとも昭和の時代にはなかったのではと思われる看板も見受けるようになって。
「付き馬」の時代とは違う新しい賑わいが生まれつつあるような気がします。

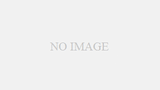

コメント
お初にコメントいたします。
ケンちゃんのところでお見かけして、浅草寺の近く(花川戸です)で生まれ育った者として押しかけて参りました。
あけおめことよろです。
浅草寺が登場する落語は、ヌーベルハンバーグさんが揚げた(『付き馬』『粗忽長屋』『あわてもの』)以外ではあたくしのデータベースによりますと……。
『姫かたり』『松葉屋瀬川』『擬宝珠』などがありました。他にも「浅草寺の鐘がボーンと鳴る」(『野ざらし』など)細々と登場する噺はいくつかあります。圓朝物(『名人長次』『菊模様皿山奇談』)にも登場します。
『付き馬』、四代橘家圓喬も速記を残しております。あたくしのライフワークでもある「圓喬全集」には今後載る予定です。
何分暇なジジイですので、ご迷惑でなければちょくちょく寄せていただきます。(^^)
立花家蛇足蛇足さん
コメントありがとうございます。
そう『姫かたり』も浅草寺境内の『市ア負けたア。』の中で起こる出来事でしたね。
すっかり忘れてました。
『松葉屋瀬川』も『圓生人情噺~中公文庫』で読んだ程度でして。
以前NHKテレビで放映していたのを見損なって無念の思いをしているのです。
『擬宝珠』は聴いたことないなと思ったら、近年現・柳家喬太郎師によって復活公演じされている噺なのですね。
蛇足さんのコメント大変に参考になりました。
改めて御礼申し上げます。
また是非お寄りくださいますようお願い申し上げます。