「そば〜う〜ぃ。」「おう、そば屋さん。」「へい。」「何ができるんだ。」「出来ますものは『花巻』に『しっぽく』でございますんで。」「『しっぽく』熱くしてくれい。」

落語好きの方には説明するまでもなく「時そば」の出だしですね。
私はNHK落語名人選の六代目・春風亭柳橋先生のLPレコードで聞いたのが最初でした。
しかし、聞いていて「はてな?」と思ったのが「花巻」「しっぽく」でした。
私の住んでいる周囲の「蕎麦屋」さんでは見たことがないメニューでした。
後に調べてみた結果「花巻」とは「かけそば」に「焼き海苔」をちぎってちらしたそばであるとわかりました。
たかだか「海苔」を散らすだけの温かい蕎麦のに、どうして「そば屋」で見ないのだろう?と思っていたら、どうも「浅草海苔」に限るというこだわりを持っている人がいるようですね。
「浅草海苔」は江戸時代初期頃から浅草川河口付近で生育し浅草紙の「紙漉き」を応用した製法で加工して売り出され、当たり前に食べられていたようですが、1.傷みやすく生産に手間がかかる。2.繁殖力が弱い。3.水温・天候・水質の影響を受けやすく収量が不安定であることから1960年になると養殖されなくなり、環境省では「絶滅危惧I類」としてレッドリストに載るぐらい希少な食品となってしまっているようですね。
21世紀に入り養殖の復活が行われるようになった今日でも5枚セットで2000円するのです。
そういう「海苔」の使用にこだわるとなると本格的な「花巻そば」は決して安値で販売できるメニュメニューではないでしょうね。
「しっぽく」なるメニューを最初に見たのは東京都内の「うどん」の店でしたね。
にんじん、大根、サトイモなどの野菜や油揚げなどの具がたくさん載っていて「時そば」に出てくる「しっぽく」もこんなに手間暇かけた具の載った「そば」が出てくるのかしらなんて思ってしまいました。
その十数年後、NHKテレビで放映していた「コメディーお江戸でござる」で故・杉浦日向子さんが語っていたところによると江戸の二八そばの屋台で売っていた「しっぽくそば」は「かまぼこ」「卵焼き」「慈姑」「松茸」(昔は安値だったそうですね。)などの具が載っていて子供さんから人気のあるメニューだったとか。
「しっぽくうどん」「しっぽくそば」ともに数種類の「具」を用いることで長崎の「卓袱料理」を模していたようなのですが、「屋台」によっては「竹輪」「麩」だけを載せて「しっぽく」を名乗っていたのもあったとかなかったとか。

このイラストのそばの具は「かまぼこ」と「ねぎ」しかないみたいだけど「しっぽく」を名乗るのは可能なのかしら?
こんな話を記していたら今夜はあたたかい「そば」か「ラーメン」が食べたくなりました。
グッと寒くなってきましたね。
皆様、風邪ひかないようにお気をつけて。


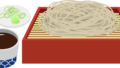
コメント