私が落語に興味持ち始めたのは昭和五十年の春頃でした。 昭和の名人の八代目・桂文楽師、五代目・古今亭志ん生師が他界して数年経って後のことでした。 それ故に両師の落語はレコード、CD、ラジオ番組、動画のVTR、DVDなどを通じて聴きました。
その中で未だに不思議に思うことがあるの出来させていただきます。 八代目・桂文楽師のレコード・CDなどの広告やジャケットなど見ると演目名で「馬のす/大仏餅」という記載を見ます。 最初は10~15分ぐらいの両演目をLPレコードの片面30分間の枠に収めようというレコード会社の意図だとばかり思っていました。
馬のす あらすじ
釣りに凝った男が釣りに出かけようとするが、テグス(釣り糸)を駄目になっている。 すると通りかかった馬方が馬を勝手に軒先につないで行った。
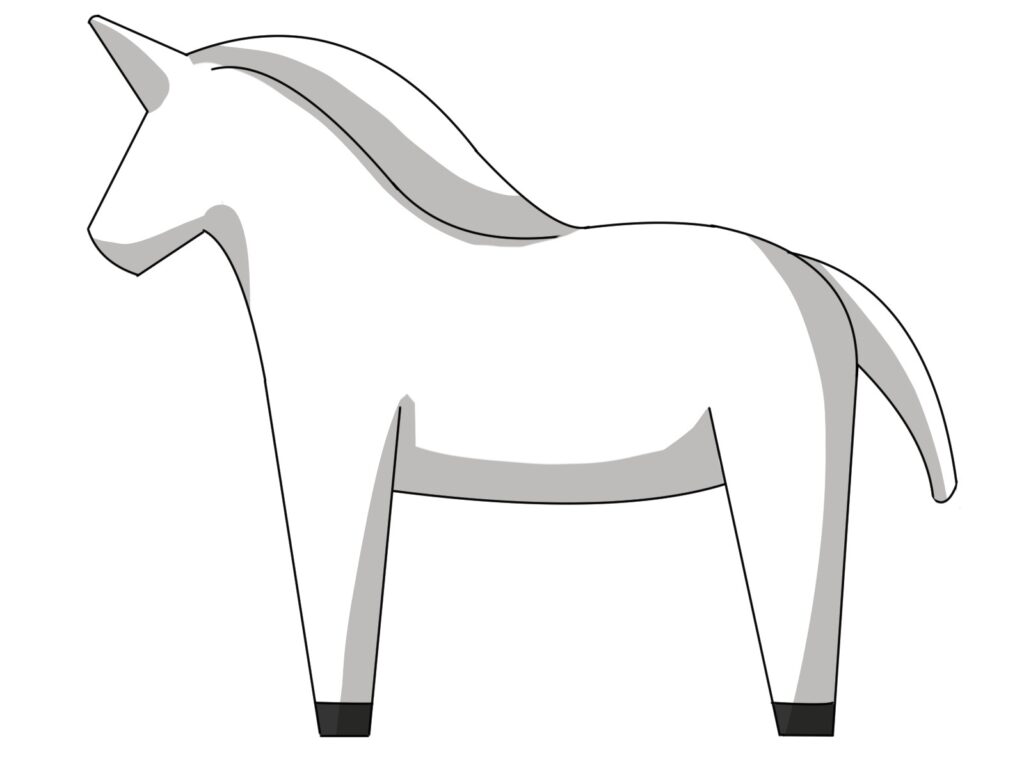
その尻尾を見て、男はテグスに使えると尻尾を3本抜いて失敬した。 そこへ通りかかったのが友達のかったのが友達の勝ちゃん。
男が尻尾を抜くのを見ていて、「お前、今尻尾を抜いたろ、えらいことをした、馬の尻尾、それも白馬の尻尾を抜くなんて」と思わせぶり、深刻そうな顔で言う。
男は気になって仕方がない。「尻尾を抜くとどうなるんだ、教えろ」と頼むが、勝ちゃんは俺もただで習ったんじゃないから、酒を一杯ご馳走しろとせがむ。 男のかみさんが他所からもらった一升壜2本をぶら下げていたのを見て知っているのだ。
仕方なく男は勝ちゃんを家に入れ酒を出す。 つまみはちょうどかみさんが茹でていた枝豆だ。

男は早く教えろとせがむが、勝ちゃんは飲んで食ってなかなか教えない。 それどころか、俺も馬の尻尾の毛を抜いてると、年配の人にこういう祟りがあると教えられ恐ろしさに震え上がっただのと、気を持たせる。 そのうちに酒も枝豆も空にしてしまった。
やっと勝ちゃん「馬の尻尾を抜くとどうなるか教えてやろう。」 男は真剣な不安な面持ちで身を乗り出す。
勝ちゃん 「馬のしっぽを抜くとね」 男「うん。」 勝ちゃん「馬が痛がるんだよ。」

大仏餅 あらすじ
ある冬の日。御徒町に店を構える、河内屋金兵衛の店先に襤褸をまとった少年がやってきた。
「おとっつぁんが怪我をしました。血止めにするので煙煙草この粉を少々ください」
その父親と言うのは目が不自由らしく、息子にすがり辛うじて立っている。
同情した金兵衛は、親子を店の奥に上げ、傷薬を渡してあげた。
「ところで、息子の歳は何歳かね?」
「六つです」
「そうかい…」
金兵衛にも息子がいるが、甘やかして育てたせいか、我侭な性格に育ってしまっている。
「さっきも、子供の『袴着の祝い』をしていたんだが、好き嫌いが多くて大変だったよ。そうだ、残り物で申し訳ないのだが…もらって行くかね?」
「有難うございます。では、ここに…」
乞食が差し出してきたのは、何と『朝鮮鈔羅(ちょうせんさはり)の水こぼし』という高級品。
「これを面桶の代わりに? 恐れ入ったな…」
「これは秘蔵品でございまして、零落しても売る気になれませんでした…」
その場で食事をすることになり、金兵衛の指示でお膳が運ばれてきた。
「八百善ですか。私も以前は、よく食べていました…」
味付けに文句ばかりをいい、料理人を困らせた報いでこのザマです…と乞食は笑う。
「しかし…。零落しても、家宝だけは手放さないとは。貴方は真のお茶人だ。何処の門人だい?」
「川上宗治の門人でした」
「貴方の名前は?」
「大変いいにくいのですが…」
意を決した乞食が話し始める。
「私は、芝片門前に住まいおりました、神谷幸右衛門と申すものでございます」
「え!? あの神幸さん? お上のご用達をなさっていた…」
変われば変わるものだ…と、金兵衛はしみじみとなった。
「そうだ。神幸さんには敵わないが、私も茶道をやっております。 いかがでしょうか、一服立てますので、飲んでいただけませんか?」 「それは有難うございます」
『お茶請けに』と用意してもらった大仏餅を、息子に一つ取ってもらい、感涙に咽びながら一口…喉につかえた。

「つかえた? 大変だ…」
慌てた金兵衛が、幸右衛門の背中をドンと一突き。
「ウプッ…有難うござヒました…」
「お!? 貴方、目が開きましたよ!」
「本当だ。でも、代わりに鼻が…」
「無理もありませんよ。食べたのが大仏餅、目から鼻へ抜けたんです」
「馬のす」は最初に現・金原亭伯楽師演をNHKラジオ「放送演芸会」で聴いて面白い話だなと思っておりました。 八代目・桂文楽師演はTBSラジオで番組名は忘れましたが八代目・橘家圓蔵師の八代目・文楽師の思い出話の後で放送していたのを聴きました。
「大仏餅」はニッポン放送の「ひやま信彦の早起きも一度劇場」で放映したのを聴きました。
その時に「?」と思ったのが、パーソナリティのひやま信彦アナウンサーが確かに八代目・文楽師の「大仏餅」を放送すると言っていたはずなのに、「釣り」の噺が始まりまったのです。 初めて聴く噺なので最初は「大仏餅」は釣りをする人なのかな?と思いました。 すると噺は「馬のす」の本筋に入っていく。 あれ?番組スタッフが間違えたのかな?思っているうちに「『馬』が痛がるんだよ。」のサゲ。 そして、一拍おいて「他人をからかって喜んでいる人がいます・・・・・落語の方でも昔は『三題噺』というものが流行いたしまして・・・・・。」と「大仏餅」のマクラに入っていくのです。 そして本筋、「目から鼻へ抜けた。」のサゲになるのですが。 まるで「馬のす」が「大仏餅」のマクラであるかのような演じ方なのです。
「馬のす」という噺自体がもともとは何かの噺のマクラに振られる小噺に過ぎなかったという話を読んだことはありますが、それにしても「馬のす」と「大仏餅」は季節も違うし、噺の中身も随分違うようだし、昭和の大名人八代目・文楽師はどういう意図のもとこういう演じ方をしたのか、私の中での大きな謎の一つです。

「大仏餅」が笑う箇所のほとんどない重くな人情噺なので先にまるでタイプの違う皮肉さもあるけど明るい噺で観客を盛り上げておきたかったのでしょうか? その辺の説明を記した文などに出会ったことがありません。
昭和46年8月31日。 国立劇場小劇場における「第5次落語研究会」の高座にこの噺をかけて「神谷幸右衛門」の名前が出ずに絶句してしまい、「また勉強し直して参ります。」の言葉を残して、八代目・桂文楽師は二度と高座に上がらなくなったそうですね。
79歳の生涯に幕を下ろしたのはその年の12月12日だそうです。
合掌

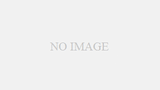
コメント
黒門町の『馬のす~大仏餅』は定番だったようですね。
音源でいうと7本中4本がこのパターンです。
『馬のす~やかん泥』も1本あります。
『大仏餅』も三題噺の説明は今の放送では無理な時代になっちゃいました。
なにせ、大仏餅・袴着の祝い・新米のめくら乞食ですからね。
黒門町が初めて『大仏餅』を耳にしたのは、移り住んでいた関西から圓朝の年忌で上京した二代圓馬の高座でした。十五日間で圓馬は『大仏餅』や『形見分け』などを掛けたようです。黒門町は前座で出ておりました。
この時圓喬が掛けた噺の一つに『鰍沢』があります。圓朝の年忌ですから真夏なのにその描写でお客が寒さを感じ袖を入れた。あの伝説を生みました。
『馬のす』は米朝の高座が印象に残っております。
枝豆の仕草が実に巧かったです。ほとんど音を出さずに手と口の動きで枝豆が見えるようでした。
立花家蛇足さん。
いつもコメントいただきありがとうございます。
「馬のす〜やかん泥」という音源もあるのですね。
それにしても、「馬のす」は人を騙して酒をただ飲む噺で、「やかん泥」は間抜
けな新米泥棒が親分と二人で空き巣に入
る噺で、満更縁が無い噺でもないのです
が、八代目・桂文楽師はどういう考えの
もとでそういう演じ方をしていたのでし
ょうか。
林家彦六師も「大仏餅」は演じていたようで「林家正蔵集」青蛙房にも掲載されてますが、単独で演じていたようですね。三代目・桂米朝師は「馬の尾」という題で演じていたのをCDで聴きましたが、仕草の見事だった噺を聴くと動画も見てみたいですね。
文楽師の事をよく知る落語通の方の話によりますと、当時、かなり忙しかった文楽師は幾つもの掛け持ちがある時は決まって「馬のす」だったそうです。
師としては時間調整のつく演りやすい噺だったのではないでしょうか?
「大仏餅」も時間としては短い噺なのでこちらも忙しい時はよくかけていたという話もあります。
hajimeさんコメントありがとうございます。
よく「ジャマにならない噺」ということを聞きますが、「馬のす」「大仏餅」もそんな噺の一種でしょうね。